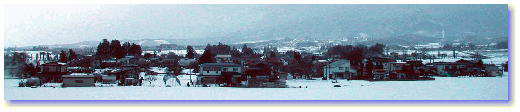
会津冬物語その5
1 序章−そば打ち体験 |2 会津漆器工房 |3 会津の食文化 |4 会津絵ろうそくまつり |5 絵ろうそく体験 |6 大正浪漫探訪 |7 酒蔵と田楽 | 8 最終章
<快適な朝>
 心地よく目覚め、最上階にある部屋の窓から外を眺めると、雪が舞っている。
心地よく目覚め、最上階にある部屋の窓から外を眺めると、雪が舞っている。東山の温泉群が目の前に広がり、対岸の山はまったくの雪景色。山の向こう側はスキー場にでもなっているのだろうか。
目の下を湯川が激しく流れている。夏にはこの川にやぐらを組んで華やかに盆踊りを繰り広げるという。
 朝風呂につかり、朝食をいただく。
朝風呂につかり、朝食をいただく。会津の米で炊いた釜飯がおいしくて、空にしてしまった。
さて、東山温泉を出発。この日のバスは昨日と違って大型に変わり、一人で二席分を使えるので快適であった。
<絵ろうそく・・・小沢ろうそく店>
最初のスケジュール 「ろうそく絵付け体験」の「小沢ろうそく店」は、西栄町「青春通り」の入口にあった。
「ろうそく絵付け体験」の「小沢ろうそく店」は、西栄町「青春通り」の入口にあった。木造の建物は明治初期建築というからすでに100年の年輪を刻んでいる。
「小沢ろうそく」さんの創業は江戸中期という。「ろうそく」専業でここまでやってこられたことは尋常ではない。長い歴史の中、波風にさらされながら、伝統の技術を守って来たことは尊敬に値する。
とくに戦後のアメリカ合理主義の台頭は逆風になったのではないかと想像する。国民は新しいものに飛びつき、古いものを排除しようとした。苦労が多かったのではないか。
<会津絵ろうそくのこと>
今から500年ほどむかし、当地の領主・芦名盛信が漆の植樹を奨励したのが始まりとされている。その後蒲生氏郷や保科正之に引き継がれ漆器と共に会津の名産品となった。漆の樹液からは塗料を、実からはロウを採取し、そのロウの炎は赤々と揺らめく特徴を持つ。材料がデリケートなため、作業は職人の手作業で行われている。現代では継承する若者も減ってしまい、絵ろうそく自体が貴重品になりつつある。


厳しい冬を迎える会津では仏壇に供える花の入手が困難で、そのかわりに季節の花を描いた絵ろうそくを飾る習慣が根付き、華やかな絵柄が生まれた。
 小沢ろうそく店では、誠実そうなご主人に迎えていただき、小学生に教えるように懇切丁寧な「絵ろうそくの実技」が始まった。
小沢ろうそく店では、誠実そうなご主人に迎えていただき、小学生に教えるように懇切丁寧な「絵ろうそくの実技」が始まった。こういった描画は感性の豊かな小学生のほうが優れている。大人は固定観念にとらわれるのと、上手に書こうとする邪念(というか欲望というか)が本来の才能の発露を邪魔する。恥ずかしがらないで、思うままに描けばよいのだが・・・。
話は飛躍する。むかし岡本太郎は講演会で二日酔いの頭を自分でたたきながら叫んだ。「子供はみんな天才だ!」と。そして「大人は考えすぎ!」とも。そのとおり、だから、大人はなかなか満足できるものを描くことができない。
しかし短い時間ではあったが、クリエイティブやイメージをつかさどる右脳を鍛錬することになり、老朽化した頭脳がしばしリフレッシュされた。
全体にかかる所要時間は40〜50分ほど。
| 絵ろうそくができるまで |
1、 芯まき 芯棒である竹串に芯紙をあて灯心をらせん状に巻く 2、 蝋がけ 蝋を何度もくりかえし重ねて塗り、一定の太さにする 3、 カンナがけ カンナでろうそくの形を整える 4、 みがき ろうそくの表面を滑らかにする 5、 絵付け 膠で溶いた絵の具で絵を描く 6、 上がけ 蝋に浸し光沢を出す 7、 頭切り、尻切り 頭部を小刀で切り出す。長さを決めて下部を切る |
会津はこの伝統ある工芸文化に光を当て、数年前から「ろうそくまつり」を始めた。冬の観光の目玉にすえようという発想だ。昔に比べたら雪も少なくなったし、高速道路網も整備され東京からはずっと行きやすくなった。
小沢ろうそく店は「絵付け体験」をいつでも受け付けている。予約可能。
住所:会津若松市西栄町6−27
TEL:0242−27−0652


<続く>
リンク (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
Copyright©2003-6 Skipio all rights reserved