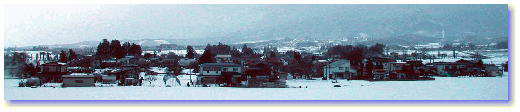
会津冬物語その3
1 序章−そば打ち体験 |2 会津漆器工房 |3 会津の食文化 |4 会津絵ろうそくまつり |5 絵ろうそく体験 |6 大正浪漫探訪 |7 酒蔵と田楽 | 8 最終章
<会津の食文化>
<宿泊は会津の奥座敷・東山温泉>
 今宵の宿は会津東山温泉は源泉掛け流し風呂の不動滝「濫觴(らんしょう)」。
今宵の宿は会津東山温泉は源泉掛け流し風呂の不動滝「濫觴(らんしょう)」。源泉は遊行僧・行基上人の開湯以来千三百年間、自噴し続け、東山温泉の源(みなもと) となっている。
ただし、残念ながらこの名湯もしばらく「お預け」。夜のプログラムがすべて終わってから。
その前に郷土食の勉強をして、それから夕食。そして「絵ろうそくまつり」の見学とぎっしり詰まっている。
 夕食前、「会津の郷土料理と食文化」をレクチャーしてくれた星さんの話は楽しかった。
夕食前、「会津の郷土料理と食文化」をレクチャーしてくれた星さんの話は楽しかった。こづゆ、ざくざく煮、しんごろう、ひしまきなど、会津に残る独自の郷土食はみな理由があって代々伝わってきた。
 南会津郡下郷町の星孝光氏(73)は会津の郷土食の伝道師。
南会津郡下郷町の星孝光氏(73)は会津の郷土食の伝道師。日夜、後進に教え伝える役目を担い県内を東奔西走している。その話は「郷土色に関する歴史の検証や栄養学や醸造学など科学的根拠に裏付けられた本格的なもの」だが、方言交じりの喋りが独特で楽しい。
時々脱線したり、誹謗中傷に走ったりするのだが、これが人柄ゆえに憎めない。いい味付けのアクセントになってしまう。聞くものを飽きさせず、あっという間に1時間は過ぎてしまった。わたしの耳には心地よく、しかも知的好奇心まで満足させてくれる。ずっと聞いていたいほどであった。
現在、会津の食文化を育てる会代表で、ニッポン東京スローフード協会会員。
<星孝光氏の話>
「食べ物っていうのは、人間が生きている以上必ず食ってきたんだわ。
日本料理が確立したのは江戸の中期。それ以降、日本全国で食文化の基本が形成された。会津もそうで、当時盛んに食っていたものが今なお残っている。
その理由はおいしいからよ。美味でねかったら食べ物は残んねえんだわ。
頭使いながらおいしい料理を作るよう、みんな苦労してきたのよ。
食が残った第1条件は美味であること。
第2番目は健康食、安全食であること。農薬、除草剤、添加物なんって当時使わねかった。
3番目は発酵、保存食が多いこと。それは生活の利便性や栄養の付加価値をつけるためだわ。
次、4番目。身近にある素材を使っていること。
日本で食文化が発達している京都は、朝廷料理、公家料理で、身分の高い、お金も持っている人たちの食文化。
ところが会津はいろり端で育まれた、庶民の食文化だ。
ところが同じ料理もあるんだわ。みがきニシンは京都と会津だけだ。ボウダラ煮は会津が発祥だが、京都には有名なイモボウなんてモノもある。会津の三大名物はそばと、田楽とボウダラ。どれもいわれがあって残ってるんだわ。
飽食時代の中で、食べ物は単に命と健康を支えるっていうものではなくて、心豊かなうるおいのある暮らしを造っていくもの。
会津に郷土食が残った理由がスローフード。物から心の時代に入っている。合理性、効率性の追求だけでは、人間の生きていく意味がなくなってしまう。
食文化を分類すっと、まず食材の揃え方。
2つ目は調理の仕方、内容。3つ目は食い方、4つ目は容器、それを食文化と言う。
同じ福島県のいわき辺りに食文化はないのよ。自然に捕れる、カツオとかサンマとか食ったって文化ではない。
そこに、すばらしい生活の知恵はあんのか。・・・・・」こんな調子で話は続いた。

<夕食の膳>

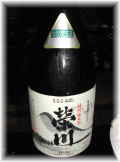
星先生のレクチャーに続き、いよいよ別室で「会津の伝統料理」をいただく夕食となった。伝統料理だけでなく、会津の伝統はおいしい酒も造ってきた。
地元の酒蔵から提供されたおいしい酒がずらりと並び、日本酒党にとってはうれしい夕食となった。
食事は星先生と宿「不動滝」板長・郡司周美さんとが時間をかけて打ち合わせた逸品の数々。全部が郷土素材の郷土料理。こんな機会は二度とない。味わって食べなくては申し訳ないのです。
<会津の郷土料理1−素材としてのエゴマ>
先生の話の続きで2〜3料理のこと。まずエゴマ(ジュウネン)の話。現在「エゴマ」が世の中に流行っているらしい。男のわたしはその手の情報に詳しくないが、エゴマはアルファリノリン酸が多く入りアトピーや喘息にも効くという。
 エゴマとは?「しそ科の植物で種類は白種、黒種とよぶ程度で、油含量は黒種が高い。やや冷涼な気候を好み、かっては東北、東山、北海道などの地域で多く栽培された。食用としては、ゴマの代用として用いられたほか、昔は灯り油として利用された。」
エゴマとは?「しそ科の植物で種類は白種、黒種とよぶ程度で、油含量は黒種が高い。やや冷涼な気候を好み、かっては東北、東山、北海道などの地域で多く栽培された。食用としては、ゴマの代用として用いられたほか、昔は灯り油として利用された。」じつは会津では「ゴマ」の栽培が気候的に適せず、「エゴマ」を栽培せざるを得なかったというのが本当の話。というと偶然の産物に聞こえるが、その産物が「身体によい」ことを会津人は自然に体感し、その習慣が地域に根を下ろし、伝統の食文化を作った。これは人の知恵。
蛇足。そもそも日本固有のゴマ文化はエゴマ文化。鎌倉時代に道元禅師がすり鉢とゴマを中国から持ち帰った。それからゴマが急速に普及したという話。
番外となるが、「品川区の地名・荏原の「荏」はエゴマと読み、むかしはその産地であったところから命名」という。
<会津の郷土料理2−鯉料理(旨煮)
 山間の会津がもともと鯉の成育に適した土地とは思えない。
山間の会津がもともと鯉の成育に適した土地とは思えない。やはりこの地に鯉料理が根ざした理由があった。
天命3年(1783)は、前年からの冷害に続いて春先の風雨、夏の寒さに見舞われ、特に東北地方は、前例のない大飢饉に襲われた。この飢饉対策として持ち込まれたのが鯉料理。
当時の家老・田中玄宰は大阪淀川から鯉を取り寄せ、各家庭の池で飼うことを奨励。海のない会津で唯一の高タンパク源となり、また、生きた魚は川魚のみであった為、魚料理の中でもっとも位の高い料理となった。
鯉の旨煮は会津の祝い膳には必ず並べられるという。
かつては会津東山温泉24軒の看板料理であったそうな・・・。
<会津の郷土料理3−ニシン山椒漬>
 会津は山国ゆえに、昔は身欠きにしんや、鱈の干物などが貴重なタンパク源であった。ニシン料理は京都の「ニシンそば」が有名で、わたしは京都に行くと必ず食べるのだが、「ニシンの山椒漬」は会津のみの料理という。
会津は山国ゆえに、昔は身欠きにしんや、鱈の干物などが貴重なタンパク源であった。ニシン料理は京都の「ニシンそば」が有名で、わたしは京都に行くと必ず食べるのだが、「ニシンの山椒漬」は会津のみの料理という。山の山椒と海のにしんを組み合わせ、作り出した一品。酒の肴には最高。
棒たら煮も会津が発祥だが、京都に「いもぼう」という有名な料理がある。
棒たらとは、たらを棒のようにカチカチに素干しにした物で、棒たら煮は、ニシンの山椒漬と同様、山国会津で海の幸を美味しく食べる為の郷土料理のひとつ。会津藩主松平容保が、京都守護職時代に京都から伝えたといわれている。
<会津の郷土料理4−こづゆ>
 会津の最も有名な郷土料理で、室町時代から伝わる「こづゆ」。
会津の最も有名な郷土料理で、室町時代から伝わる「こづゆ」。冠婚葬祭など、人が集まる処では必ず作られる会津だけに伝わる伝統料理。
昔は、お膳を家に手みやげとして持ち帰り、こづゆを酒の肴として食した。
何杯おかわりしても良く、「重ねのつゆ」「替えづゆ」「おつゆ」から変化して、「こづゆ」と呼ばれるようになった。器も熱いうちに何杯でもおかわり出来るように、平たい手掌皿(洗朱)が決まっている。食と器の文化でもある。
ひとつの器の中に山の物、海の物が盛り沢山の郷土料理。
<会津の郷土料理5−はっと
 「はっと(う)」は尾瀬への福島側からの入山口・桧枝岐村の料理で、そばを平に延ばした状態で、そば切りにしないでいただく。そば粉とえごま、砂糖、塩で練る。しゃぶしゃぶにして食べるのもいいらしいが、この夜は甘みのある十念掛け(エゴマのタレ)でいただいた。
「はっと(う)」は尾瀬への福島側からの入山口・桧枝岐村の料理で、そばを平に延ばした状態で、そば切りにしないでいただく。そば粉とえごま、砂糖、塩で練る。しゃぶしゃぶにして食べるのもいいらしいが、この夜は甘みのある十念掛け(エゴマのタレ)でいただいた。わたしにとっては初めての料理かな?
その他「ざくざく」「しんごろうさん」「つゆ煮染め」「納豆ひしお」「三五八漬」「ひしまき」などにも言及されたが、時間足らずの残りは、食事をいただきながらの解説となった。


もっと楽しい話がたくさん聞けたのと、せっかくのおいしい料理をじっくりいただけたのにと・・・・・。
<絶対的な土産>
もうひとつ。あえて苦言を呈すると、これだけの伝統料理がたくさんあるのに、お土産として持ち帰りたいと思う絶対的な名物が、酒以外にない。これは寂しい。
「会津に行くのなら、これを買ってきて!」と頼まれるような手ごろな土産。
新潟の笹団子のようなもの。山梨なら信玄もち、京都の八橋、名古屋の外郎、仙台の「萩の月」のように、そこにしかないものがあってもおかしくないのに、それがない。全国的にこれはといえる著名な土産がないのだ。
ぜひともつくって欲しいものだ。
|
1 小煮物 こづゆ |
| 会津東山温泉・不動滝「濫觴(らんしょう)」 (HPへリンク) TEL 0242-26-5050 FAX 0242-26-5052 〒965-0814 福島県会津若松市東山町湯本川向216 |
<続く>
リンク (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
Copyright ©2003-6 Skipio all rights reserved