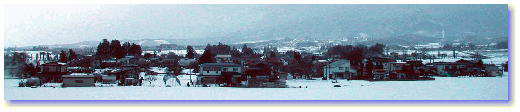
会津冬ものがたり
−伝統産業と食文化を求めて 2004年2月14・15日−
1 序章−そば打ち体験 |2 会津漆器工房 |3 会津の食文化 |4 会津絵ろうそくまつり |5 絵ろうそく体験 |6 大正浪漫探訪 |7 酒蔵と田楽 | 8 最終章
<序 章>
「ふるさと往来クラブ」の主催する「冬の会津・体験ツアー」に参加した。このクラブの目的は「都市(ふるさと)と農山漁村(ふるさと)とが人・モノ・情報の交流を通して町おこし・村おこしをする、その支援をする」というもの。耳慣れないことばだが、地域経済活性化のための「産業栽培」を目指すNPOの団体である。
今回は雪深い会津を訪ねて、その産業や食文化を体験するという企画であった。

会津商工会議所の誠実な若いスタッフは説明してくれた。
「平成4年会津を訪れた観光客は380万人でしたが10年後の現在は270万人と7割に落ち込んでいます。産業においても同じような数値を示しています。会津の主要な地場産業である漆器や清酒の出荷額も漸減しています。製品によっては半減してしまったものもあります。」
これは想像を絶する由々しき事態である。
地場産業の企業経営の苦しさが想像できる。たぶん一部の地方を除いて地方はみな同じような危機的状態にあるのではなかろうか?(都市も同じなのだが・・・。)
しかしながら政治の舵取り役である小泉政権は何も助け舟を出してくれない。いつも「みんなで我慢しましょう!」を連呼するだけだ。そこで会津は立ち上がった。自らの手で観光資源や地場産業を見直してその活性化に取り組もうと。
今回の旅行のテーマは「会津の活性化のために」である。
<蕎麦打ち体験>
近頃は都会でも蕎麦を打つ人が増えてきた。
一種のブーム的様相にも思える。それだけ男が暇な時間を持つようになったのか、高齢化社会を迎えた若い蕎麦好きの熟年が増えたせいなのか、はたまた健康志向のあらわれか。いずれにしろ「たかが蕎麦、されど蕎麦」ということばを多く聞くようになった。
 猪苗代インターで高速道を降り、雪道を走って最初に立ち寄ったのが「会津若松市基幹集落センター」で、ここが地元「湊町産・蕎麦打ち体験」の会場となった。
猪苗代インターで高速道を降り、雪道を走って最初に立ち寄ったのが「会津若松市基幹集落センター」で、ここが地元「湊町産・蕎麦打ち体験」の会場となった。
広々としていて、ふだんは体育館として利用しているようだが、すでにそこには何組かの蕎麦打ちセットが準備され、いまや遅しとわたしたちを待ちかまえていた。
この地域ではすでに「体験村」と銘打って、さまざまな農業体験イベントを実施しているとのこと。
蕎麦を「名物として売っていきたい」という熱意がうかがえた。
<挽きぐるみの田舎そば>
 「田舎蕎麦伝承会」の代表の方が簡単に説明し、3人ずつのグループに指導員が一人ずつついて蕎麦打ち体験は開始された。
「田舎蕎麦伝承会」の代表の方が簡単に説明し、3人ずつのグループに指導員が一人ずつついて蕎麦打ち体験は開始された。
 わたしのグループには、知人宅にホームステイしている米国からの留学生アッシーナさんが加わったので、彼女に日本の食文化体験の主役として活躍してもらった。
わたしのグループには、知人宅にホームステイしている米国からの留学生アッシーナさんが加わったので、彼女に日本の食文化体験の主役として活躍してもらった。
今回は粗挽きした挽きぐるみの粉(甘皮と呼ばれる種皮まで一緒に挽きこむ挽き方)を使用し、しかもつなぎを使わない「蕎麦粉100%の10割蕎麦(難しい)」を打った。工程において江戸前の打ち方とは少しずつ違っていたのが興味深かった。(参考→すでにアップした蕎麦打ち工程)
 その1。
その1。
温湯ではなく熱湯を注すこと(湯ごねという)と、注した湯の量が多かった。空気が非常に乾燥していたからだろうか、江戸前は総量の40%を基準とするが、50%を入れた。そのうえ練りの仕上げ段階で今度は水を10%ほど足している(水ごねという)。それに菜箸を使っていたのもユニーク。
 その2。
その2。
ある程度丸く延ばしてから周囲をぐるりと切り取ってしまった。切り取ったものを丸めて真ん中に置き、蕎麦粉で馴染ませ、もう一度延ばす作業を入れている。これは合理的であると感じたが・・・。
その3。
四つ出しをしない。角を四角くする作業を省略している。
処変われば技術も異なるのは当たり前。
<江戸と会津の蕎麦文化>
「江戸の蕎麦と会津の蕎麦の違い」は夕刻、後述する星先生のレクチャーの中で説明をいただいた。
「江戸の蕎麦文化は更科文化。一番粉を利用する純白の更科は旨みを感じるデンプンが多い。それは味覚に訴える蕎麦だから商売のための蕎麦になる。あるいは商売のための蕎麦だから旨くなくてはならない。」
これに対し、「会津の蕎麦文化は三番粉文化。要するに田舎蕎麦のことで、こちらは、デンプンは少ないがたんぱく質が多い。ハレの日にお客様にふるまう『もてなしの蕎麦』で、栄養がある。旨みより歯ざわり、歯ごたえ、のど越しという実質的価値が高い。」という指摘であった。
これはわたしが一茶庵で聞いた話だが、「更科はつなぎの力となるたんぱく質が少ないため、100%で打つのは難しい。」つなぎとなる小麦粉で打ちやすくしているようだ。(二八蕎麦など)
 会津の蕎麦は保科正之(家光の異母弟)が前封地・信州高遠から持ち込んだという話も興味深かった。無類の蕎麦好きであった正之公は産地の更級の「級」の文字を自身の保科の「科」にしてしまった。「更科蕎麦」の誕生にまつわる本当の話。
会津の蕎麦は保科正之(家光の異母弟)が前封地・信州高遠から持ち込んだという話も興味深かった。無類の蕎麦好きであった正之公は産地の更級の「級」の文字を自身の保科の「科」にしてしまった。「更科蕎麦」の誕生にまつわる本当の話。
ま た薬味となる辛味大根も高遠から持ち込んだ。会津には今でも大根で食する「高遠蕎麦」を標榜する店が多い。
ちょうどお昼を過ぎておなかの虫がグーグーと鳴き始めるころ、今朝のうちに地元のプロのみなさんが打った蕎麦をいただくことになった。
自分で打った蕎麦をなぜ食べないの、という質問は当然ありましょうが、とても食べられる代物ではない・・・・・ではなくて、「これはお土産として持ち帰ってください。」というやさしい配慮がありました。それに蕎麦は打ちたてよりしばらく時間をおいたほうがおいしくいただける。したがってそれぞれが楽しみにしている家族の翌日の夕飯となる運命となった。
| 田舎体験募集!! |
| 生産者:会津粗挽き田舎蕎麦伝承会 問合せ:会津若松市役所農政課内 TEL:0242−39−1253 ■なお「種蒔きから始める本格的そば打ちコース」と題するプランも用意されている。 ・そば種蒔き体験 H16.8.1(日) ・そば打ち講習会 H16.11.7(日) ・会員特典 そば粉1kg 講習会昼食(新そば)無料 ・会費 7000円 その他「田植えから始める自分だけの吟醸酒作りコース」「苗植から始める新鮮野菜もぎとりコース」「手前味噌作りコース」なども用意されている。問い合わせは上記またはHPへ。 http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/j/sangyo/nogyo/green-tourism/ 田舎生活を体験するチャンスをお見逃しなく! |
リンク (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
Copyright©2003-6 Skipio all rights reserved