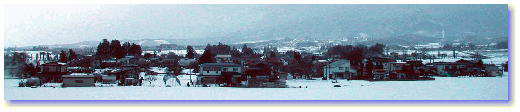
会津冬物語
その4
1 序章−そば打ち体験 |2 会津漆器工房 |3 会津の食文化 |4 会津絵ろうそくまつり |5 絵ろうそく体験 |6 大正浪漫探訪 |7 酒蔵と田楽 | 8 最終章
会津絵ろうそくまつり −ゆきほたる− (2月14日夜)

数年前から始まり今年は5回目を迎えるが、会津藩主松平家の庭園「御薬園」と名城「鶴ケ城」で「絵ろうそくまつり」が開催されていた。
夕食後、疲れもみせず元気に出かけたのは、この夜の祭が会津旅行を飾る最大のイベントとして、おおいに期待していたからである。
 暗闇の中にろうそくの火がゆらゆらと揺れる。これは幻想的でなければならない。
暗闇の中にろうそくの火がゆらゆらと揺れる。これは幻想的でなければならない。純白の雪も演出のひとつとして欠かせない。しかも真冬の夜の行事なのだから寒くなければならない。
札幌の雪祭のような華やかさは必要ない。雪深い会津のシンシンと降り積もる白い闇の世界に揺れる小さな光。それがわたしの「ゆきほたる」のイメージ。ここは会津なのだから・・・。
<御薬園>
 「御薬園」は中央に「心字の池」を、その中島に楽寿亭を建て、池の周辺には巧みに石を配してある。磐梯山や東山を借景に取り込んだ山水庭で、昼間の散策も捨てがたい。
「御薬園」は中央に「心字の池」を、その中島に楽寿亭を建て、池の周辺には巧みに石を配してある。磐梯山や東山を借景に取り込んだ山水庭で、昼間の散策も捨てがたい。しかし今回は夜、この夜の御薬園は・・・・・。
くりぬいた孟宗竹の中に絵ろうそくが納まり、「心字の池」を取り囲み、回遊する市民の足元を照らす。
これはいにしえの幽玄・幻想の世界。琴と横笛の生演奏による音色が静寂の闇に流れ、着物姿の妙齢のご婦人が謡い、彩を添える。

<鶴ヶ城の絵ろうそく>

 この時刻から雨脚がいっそう激しくなってきた。
この時刻から雨脚がいっそう激しくなってきた。天守閣に上る。
横殴りの雨は高みにある天守を襲い、風雲急を告げていたが、それでも絵ろうそくの光は気丈に灯り続けた。
城内の、普段は芝生がはってある庭園の白い世界に「ゆ・き・ほ・た・る 2004」の文字が明確に読み取れた。
このイベントは若いボランティアの支援を得て開催されている。
若者は、このようなイベントに参加することによって郷土に対する意識を向上させ、誇りをもつ。
最初は幼稚なイベントも続けることによってやがては本物になる。
何千本かの揺れる絵ろうそくに「会津魂」を見た。
目を上げて周囲を眺望すると、会津の町の灯が雨にぬれて、海に浮かぶ漁火のように見えた。

<自噴の源泉かけ流し宿>
そぼ降る雨の中を引き返し、バスに乗り込み宿に戻ったら、時計の針は9時を回っていた。冷えた身体を絶妙の温泉で温めた。源泉賭け流しの湯は57℃と高く、内風呂は43−4℃とやや熱め。逆に露天はぬるめ。露天でゆったりと手足を伸ばす。早朝から動き回った一日の疲れが緩やかに抜けていくようで心地よい。
「不動湯」さんに関する逸話。
ここには三つの源泉がある。そのひとつは「猿の湯」というのだから、昔は猿があそびに来たのだろう。その湯で土方歳三が戦傷を癒したという。
慶応4年という年は慌しかった。土方は1月3日鳥羽伏見で破れ江戸に戻り、3月5日には甲府で粉砕され、3月20日過ぎには下総流山(近藤逮捕)から逃れて会津にわたり、5月11日函館戦争で戦死している。
猿の湯に浸かることができたのもわずかの日々ではなかったか。NHK「新撰組」の終盤でそのあたりは放映されるかもしれない。
入浴後、しばし会津銘酒をいただいきながら熟年男の雑談。11時過ぎには横になった。
雨は夜の間にいつの間にか雪になったようだ・・・。
<続く>
|
御薬園 TEL 0242-27-2472 FAX 0242-29-1322 |
リンク (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
Copyright©2003-6 Skipio all rights reserved