<平潟と鮟鱇鍋>
あとは一目散で平潟に向かうだけ。
ナビゲーションをちょっと頼りないママさんにお願い。予め道を示唆しておけばきちんと役割を果たしてくれます。袋田から461号線を高萩に向かって、田舎道を走りました。道路標識を見落とさない限り確実に導いてくれます。途中何箇所かの峠越えはカーブの連続で、これで国道かと思うほどの細い道もありました。またいくつかの村落は、日本人の原風景ともいえる里山の落ち着いた光景を見せてくれました。昔は日本全国どこに行ってもこの景色がありました。藁の匂いがする暖かく懐かしい光景です。
途中この狭い道で何台かの消防自動車とパトカーにすれ違いました。翌日のニュースで「茨城県で山火事発生、住民が避難」とのこと。なんと3日間も燃えつづけていました。けっして私が放火したわけではありません。念の為。
さて、38.5キロを小1時間走って高萩の高速道下へ到着。高萩から北茨城へは高速道を利用。あとは6号線を北上するだけ、山で点灯していた車のヘッドライトも海岸道路でははずかしかいものでした。

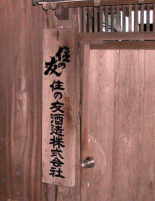 小さな港がありました。天然の良港です。この港は優れた歴史を誇ります。江戸時代、東廻海運の寄港地として伊達藩が開港、重要な役割を果たしてきました。町がしっかりしているのはそのせいでしょうか。蛇足ですが、遊女の方もいらしたようです。
小さな港がありました。天然の良港です。この港は優れた歴史を誇ります。江戸時代、東廻海運の寄港地として伊達藩が開港、重要な役割を果たしてきました。町がしっかりしているのはそのせいでしょうか。蛇足ですが、遊女の方もいらしたようです。港の小路は、季節がら人通りも少なく、ひっそりとしています。
「魚の宿まるみつ」の灯りだけが、明るく私たちを迎えてくれました。
ほっとする瞬間です。全走行距離238キロ。
 部屋に落ち着く時間も無く、風呂へ。ここは温泉なのがありがたい。大きめな風呂に一人でゆったりと浸かる。天国に来た気分です。温泉は気持ちをほぐし、身体を温め、とにかくほっとさせてくれます。夕食への期待や明日の行程を考えたり、一日のうち一番リラックスできる時間です。
部屋に落ち着く時間も無く、風呂へ。ここは温泉なのがありがたい。大きめな風呂に一人でゆったりと浸かる。天国に来た気分です。温泉は気持ちをほぐし、身体を温め、とにかくほっとさせてくれます。夕食への期待や明日の行程を考えたり、一日のうち一番リラックスできる時間です。ちなみにここの泉質は塩化物泉で、神経痛や筋肉痛、疲労回復に効能あり。上がり湯は使わず。
さて、夕食は6時20分に広間で始まりました。
さあメニューはなんでしょう。東京12チャネルのこの種の番組を見なれている私は過度の期待をしています。まずこの日、港に上がった魚介類のおさしみ。かんぱち、いなだ、スズキ、たこの刺身、ズワイガニ、ボタン海老にツブ貝、加えてウニも適量。これらはコリコリ、シコシコとみな新鮮でおいしい。また、いさきが丸ごと塩焼きで出てきました。
さてメーンディッシュの鮟鱇鍋(料理法)です。期待していたより量が少ないのが不満です。でもこんなものでしょうか? 鍋のスープは、あん肝をすりつぶし味噌と合わせたものを使っています。こちらではドブ汁と呼んでいます。多少、魚くささが残りますが、白菜から出る水分の甘味とからまり美味です。コクがあります。
鮟鱇の身は蛋白ですが、その反面、濃厚な肝が補ってくれます。あんこうは捨てるところが無い魚で、皮から内臓まで全てを人間に奉げてしまいます。皮はゼラチン質でおいしく、骨までコリコリとやわらかで食感が良い。難点は身が少ないこと。
あっという間に鍋の中は空っぽになってしまいました。
ご飯を入れて雑炊にしたかったのに、とママさんは嘆きました。
デザートは初物の西瓜です。
ほぼ全部を平らげて見た我がお腹は・・・。臨月を迎えた娘のお腹のようでした。これだけ食べたら体重は確実に危険水域を越えるぞ、と天の声、いや会社の保健婦さんの恐ろしい顔が目に浮かびました。。。
正直に言えば鮟鱇鍋は期待に答えてくれませんでした。むしろ、土産に購入したアンコウセットの方が美味でした。それと気になったことが一つ。給仕さんがうろうろと催促をして落ち着きません。旅に出た時の食事ぐらいは時間を気にしないでゆっくりしたいのに・・・。
この日はそのまま布団に倒れこんでしまいました。ぐっすりと熟睡。
前日、部屋に一枚のメモがありました。
いわく「明日の日の出は5時57分です。」加えて「見学場所はいずれも歩いて5分です。」
こんな機会は滅多にあるものではありません。しっかりと5時20分に目覚ましをセット。
春とはいえ3月中旬の早朝はまだ寒い。持ってきたダウンのジャンパーを着込み、港とは反対の随道を抜け、肩を丸め腕組みして歩くことしばし、長浜海岸、通称・鳴砂海岸に5時40分に到着。しばらく待つことにしました。左手の海に突き出たテトラポットの上で釣人が糸をたれています。
 既に夜はしらじらと明け始め、太平洋が少しずつ明るくなっていきます。
既に夜はしらじらと明け始め、太平洋が少しずつ明るくなっていきます。この時刻を黎明というのでしょうか。
砂浜の上空は雲一つ無く透き通っているのですが、彼方の水平線上に雲が少しかかっています。その雲が明るくなってきました。最初はうっすらと黄色に、少しずつ黄色が赤みを増して水平線全体に広がっていきます。
 5時54分、水平線の雲の切れ目が黄金色に輝いています。
5時54分、水平線の雲の切れ目が黄金色に輝いています。太陽が上り始めています。少しずつ、そしてす早く、まるで生き物のように上がっていきます。
5時57分、一つの雲の層に太陽が頭を押さえられています。しかし少し離れた上の雲は金色に輝いています。1分、2分と時間が経過します。洋上の明るさは刻々と変化しつづけています。
 6時を迎え、ついに太陽の光が丸い光彩を放って海を越えてやってきました。一条の黄金色の光束です。瞬間、太陽を独占していました。例えようもなく感動的で、思わず手を合わせてしまいました。
6時を迎え、ついに太陽の光が丸い光彩を放って海を越えてやってきました。一条の黄金色の光束です。瞬間、太陽を独占していました。例えようもなく感動的で、思わず手を合わせてしまいました。10分ほどの短い時間でしたが、荘厳な儀式に立ち会ったかのようです。毎日登ってくる太陽ですが、こうやってじっくり見たことはほとんどありません。それだけに感動は新鮮です。
じっくり考えれば、太陽は人類の源です。太陽によって人類は生かされてきています。
原始の時代は日常の中でもっと緊密に太陽や月・星などと接していましたから、自然に対する信仰心が篤く、ことあるごとに何らかの形で儀式の中に取り入れてきました。風水等もその中から出てきたものでしょう。
多忙な都会人はほとんど思いの及ばない、また経験できない世界であり、貴重な体験をしました。
おかげで「タイしゃぶ」付きの朝食は格別美味しくいただくことができました。
<続く> <六角堂と岡倉天心>
Copyright ©2003-6 Skipio all rights reserved
