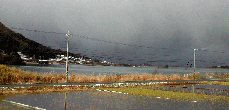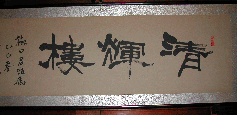2002年暮から2003年正月にかけての家族旅行
第1章 冬の丹後半島・天橋立
第2章 瀬戸内・宇野の朝日
第3章 倉敷・尾道・しまなみ海道
第4章 松山と道後
第5章 京都・宇治
1・・・冬の丹後半島
(12月29日・30日正月に向かう)
慌しく混雑する暮の東京駅から新幹線で下るわたしたちを、快晴の富士山が見送ってくれた。
雲ひとつない霊峰の姿は眺めていて、いつまでも飽きない。
浜名湖も清清しい。一年の垢を洗い流してくれるかのようであり、またこの日の旅立ちを祝してくれているようでもあった。
今年も、一族郎党が集結し正月を祝う。昔はどの田舎でも、どの家でもそんな光景が普通にあった。今では考えられないかもしれないが、生活が苦しければ苦しいほど家族は結束し、お互いの活躍を称え無事を愛で、明日への努力を誓い合った。その合言葉は、今は語ることもなくなった「夢」。「夢」を語らなくなって何年が過ぎ去ったことか。しかし「夢を夢見る」のは古今東西、普遍的な人間の欲求であり、権利でもあった。
今回の旅は、一族郎党が、その夢を実現するための「浮橋」探しの旅であった・・・。
<<ダークグレーの天橋立>>
<珍道中>
家族とは別行動の「親父と息子君との二人きりの珍道中」は12月29日に始まった。
東京から京都へ、そして丹後へ・・・。
暮れの混雑する京都駅を出発した山陰本線「特急・丹後ディスカバリー」は山間部を走り、西舞鶴で車両が切り離されたあと、北近畿タンゴ鉄道と名前を変えてさらに奥深く走る。
その天橋立駅で降りた。この鉄道はもともとJRの支線であったが、合理化の嵐の中で整理されかけたところを、地元が第三セクターの経営スタイルに転換して運営している。残念ながら赤字続きという。こういった状況は地方では当たり前になっているように思うのだが、赤字を続ける経営は現代では容認されず、それゆえ旅人は、なんとか妙手を考え出して正常な経営をしてほしいと、願わざるを得ない。
<松葉かに>
小雪混じりの天橋立駅で若い係の女性に案内を請い、近辺の名所旧跡地図を手に入れた。地理に不案内なので、とりあえず地図に従って観光船乗り場に向かうことにした。
海はすぐ近くまで迫っていて、駐車場の横がみやげ物売り場になっている。というより「松葉かに」売り場といったほうが適切で、いたるところに「松葉かに」の宣伝文句と写真がべたべたと貼ってある。そう、今宵の夕食のことを想像すると寒さの中でも生唾が出てきて仕方ないのだが、ひそかに(がまんがまん)と自分に言い聞かせた。そもそも朝から時間の折り合いが悪く、いまだ昼食を摂っていない。生唾も仕方なし。ゴム長靴を履いて、黒セーターの上に黒ジャンパーといういでたちの老爺が店番をしていた。
<瀟 洒>
平安遷都直後の808年創建という文殊堂(本尊は文殊菩薩)の境内を抜け、観光船乗り場にいたると、驚いたことに、すぐ目の前が「天橋立」であった。ここから1キロほど先まで、日本海の潮流によって寄せられた砂が湾を横切る形に砂嘴を作り、その砂嘴が「天橋立」と名づけられたのである。
田山花袋は日本三景を比べ「三景の中で瀟洒な感じがするのはここだけである。さびしい、やさしい、当り気のないところは他の三景に見ることはできない。しかし傘松の上の眺望よりも橋立神社のある松の中を歩くときのほうが、いっそう心持が良かった」と随想している。
小雪が舞って凍えるような寒さの中、花袋がいう橋立の松林の散策でもないだろうと、船で見晴らしの良い対岸に渡ることにした。観光船は15分ほど湾内を走り、橋立の一方の先端にあたる「一の宮桟橋」に着くと、ここにも神社がある。その「丹後一の宮・籠神社(このじんじゃ)」は古代(神代の昔:天照大神を祀る)からの国宝系図を有する神明造の格式高い神社で、元伊勢とも呼ばれている。天橋立はかつて籠神社の参道であったともいわれているが、その景観から、有史以前の神話時代のことであればたしかに白砂青松の参道であったに違いないと素直に肯けるのである。

< 雪 >
ケーブルに乗って傘松公園に上がる。
雪は降ったり止んだり。船着場で働く年配の職員が話してくれたが、昔はこのあたりも雪が多かったようだ。一度降った雪が根雪となり、その根雪の上に新しい雪が降り積もる。さらに次の雪が・・・「子供のころは二階から出入りしたこともある」という。
現在の光景からはとても信じられないが、今よりずっと寒かった時代に、そのころは除雪作業なども効率的にできなかっただろうから、降り積もる雪にすっぽり包まれて、雪と共存しながら生活を営んでいた人たちの苦労は容易に想像できるのだ。
<<極楽への階段>>
さて高台の傘松公園から見下ろす天橋立の眺めは、一面のグレーの世界。
広がる海もグレーなら、雪の舞う空もグレー、海を分けるように真ん中を走る砂嘴・日本三景「天橋立」もグレーに覆い隠され、色を失ってしまった。寒さに震え、小高い岡の上から小雪混じりの風に吹かれながらこのモノトーンの世界をじっと見詰めていると、眼下の天橋立は地獄へいざなう悪魔の橋にも思えてしまう。
暗い想念を打ち消し、目を移すと傍らに見事な大樹が枝を下ろして立っている。
(桜か・・・桜の咲くころはさぞかし華やかだろうな。青く澄んだ空と深い群青の海の中に、くっきりと緑の橋立が白砂とともに浮かびあがる。この橋立は極楽に上る階段になり、その階段は薄いピンクの桜の花道となる)
神話の世界で昔の人がそういう思いをもって、橋立を祀り上げたことは十分に頷ける。
それは・・・阿蘇海と宮津湾に浮かぶ夢の浮橋。
<股のぞき>
寒さに縮んだ身体を折り曲げて「股(また)のぞき」に挑戦した。
天橋立に背を向けて立ち、両足の間から橋立をのぞき見るという風習で、この高台にはのぞき台が用意されている。いい大人が子供じみた股のぞきをするのは照れくさくもあり滑稽だが、周囲に観光客がいないのを確認して、おもむろに身体を折ってのぞいてみた。
天にかかる橋とか、天に昇る龍のように見えるということだが、灰色一色の世界は逆さまに見ても同じ灰色の世界。記念写真だけは嬉々として股の下から撮ったのだが、これはプリント写真の天地を逆にすれば同じことで、帰宅後家人に馬鹿にされてしまった。
帰りは幸いなことに桟橋から宮津まで戻る船が待っていた。一日に一本しかない定期船で、これはタイミング的にも幸運というしかなかった。
橋立の砂嘴を左に眺めながら阿蘇海から宮津湾に抜け、今宵の宿・丹後宮津に上陸した。
(左 廻船橋が開いた)
この日は夕食への期待もあって昼食を抜いてしまったから、さもしくもあった。おなかがすいていた。傘も持たず雪に降られ寒くもあった。そんな橋立は墨絵のように静かで、俗人の欲望をあざ笑うかのような枯れた印象を残してくれた。
はし立てに 暮れて宮津の 灯に泊り
はし立ての うすずみ色に 小雪舞う
ついでに歌仙の詠まれた詩歌を調べてみた。
大江山 いくのの道は 遠ければ
まだふみもみず 天橋立 小式部
八朔や 天の橋立 たばね熨斗 芭蕉
春の海 ひねもすのたり のたりかな 蕪村
<<文人墨客の宿・清輝楼>>
<イメージ>
今宵の宿は宮津「清輝楼」。
そもそも丹後半島への第一の目的は「松葉かに」を食することで、宿泊は宮津である必要もなかった。
広範囲に城崎温泉、香住、網野など「丹後かに街道」の数ある旅館を調べ、その中から「文人墨客の宿」というキャッチが気に入って決めたといういきさつがある。
冬の城崎温泉の雪見酒にも心魅かれたが、そちらは志賀直哉を読んでからということで今回は先送りにした。そしてこの選択はまさに正解であった。
<丹後宮津>
さて、丹後宮津という町の歴史のこと。
この町は細川(1580)・京極など戦国に活躍した有力大名の初期の治世を経て、江戸時代初期に京極高知の子・高広が7万8千石で宮津に封じられたところから本格的な街づくりが始まった。京極氏のあと、永井氏、阿部氏、奥平氏、青山氏と藩主が代わり、宝暦9年(1759)より本庄(荘)氏が治め、幕末まで統治が続いた。
<細川幽斎>
偶然知り得た話。
時は天正10年(1582)6月、明智光秀は本能寺に信長を急襲し、各地の反信長勢力に檄を飛ばし「天下取り」を宣言した。
光秀の思惑は、秀吉以下が派遣先から帰るまでの短時間で足元を固めてしまうことにあった。その戦略上、もっとも頼りとしていた武将に出兵を促した。
しかしそのとき宮津にいたその男・細川藤孝(幽斎)・忠興父子は剃髪・隠居して動かず、その後秀吉側についた。裏切りというべきか変節というべきか、そのため光秀の大いなる野望は潰えた。
お家だいじのしたたかな選択が細川家にはあった。
もう一つ細川忠興の妻・ガラシャのこと。
ご存知のように細川ガラシャは明智光秀の三女で本名は「玉」、美貌の誉れ高く、加えて才女であった。
幽斎はこのとき玉を丹後の山中へ幽閉して義絶のポーズをとり、豊臣の疑惑の目から矛先をかわした。
時代は下り慶長5年(1600)、細川家は徳川方の忠実な家臣であった。たまたま忠興が家康に従い上杉征伐に出陣して留守中、石田三成に攻められ、ガラシャは大坂方の人質を迫られた。彼女は夫の足手まといになることを恐れ、家老の小笠原小斎に長刀で胸を突かせた後、館に火を放って落ちる屋敷とともに悲運の最期を遂げた。
武士の妻らしく細川家の面目を保った。
ちりぬべき 時知りてこそ 世の中の
花も花なれ 人も人なれ
辞世の句だが、非常に強い。強い人物像が浮かび上がる。
このように書いてくると、細川家は女性が優位のようである。
第79代総理大臣になった18代当主・細川護熙氏にとっては(祖先の苦労が実を結び、やっと天下を制した)と溜飲を下げたことだろうが、いつの間にか身を引いてしまった。
これも細川家の先祖代々引き継いだ「したたかな選択」というものだろうか?(失礼の段はお許しを・・・)
宮津は天然の良港で、九州から北海道に向かう北前船の寄港地として大いに栄えた。
実に北前船のもたらしたオランダ絵皿が旅館にも残っているという。現在の人口は3万人を切るというから、昔の栄華が偲ばれるという言葉も大げさではない。
「三上家」という豪商の邸宅も文化財として保存されている。
<文人の宿>
清輝楼は1758年というから江戸中期の創業で、まもなく250周年を迎える。
時の城主が文化をだいじに守り育てたという土地柄も手伝い、創業当初から京都の土佐派、円山派、狩野派らの絵師たちが逗留したという由緒ある宿であった。
明治以降は野口雨情、菊池寛、吉川英治、河東碧梧桐などそうそうたる作家・詩人たちが滞在し詩歌、書画などの作品を数多く残している。
それらの実物作品が館内のいたる所に掲出されており「小さな美術館」さながらである。
吉川英治は昭和18年6月(当時51歳)ここに逗留して、天橋立を「松 々 々 どれも 日本の すがたかな」と詠んだ。
太平洋戦争に従軍し、海軍機で南方を一巡した直後の書である。彼の心は如何ばかりであったかと思うのだが、吉川が書いた直筆がここにある。
この歌は奥多摩・青梅の吉川英治記念館で自作の花瓶にも描かれているという。吉川がこの歌を気に入り、大事にしたという状況が垣間見える。
宿の主人は、「吉川が愛でた橋立の松は『日本』そのもので、これは日本を象徴する富士山の清純美につながる愛国思想である」と吉川を解説する。
仲居さんの話では「野口雨情とも何がしかの深いかかわりがあった」らしく、かたつむりやかえるなど愛らしい小動物をテーマにした書画が館内に掲出されていた。
<<かに三昧>>
さて夕食は期待に違わない松葉のかに尽くし。
仲居さんは、わたしたちの「かには焼くのが、一番おいしい」という意図を汲んで、かに鍋のための材料すら、そのほとんどを炭火で焼いてくれた。鍋用のだし取りに少しだけ残して。
甲羅の味噌も日本酒を入れて暖め、ぐいと一口、これはいける。ぐいぐいと一気に胃の中に流しこんだ。もうたまりません。
かにはいいことばかりではなく、罪もある。
会話を遮断してしまう。無言になって目の前のかにと対峙し、果敢に食する。おかげで息子君とじっくり話そうと思っていた時間がなくなってしまった。世の中のこと、仕事のこと、人生のこと、恋愛のこと・・・。
中盤から鍋と酒に移ったが、最後はもう食べられないと思った雑炊が、すいすいと胃の中に入り食事は終わった。もう何もはいらない。何もいらない。一刻も早く横になりたい気分だった。
布団の足元に、今では珍しくなった豆炭のカイロがはいっていた。由緒ある建造物のせいか、暖房を現代風に廻すのに限界があり、それゆえの寒さが欠点といえば欠点。シンシンと冷える師走の旅館であったが、温泉とカイロのおかげでぐっすり眠れた。
<歴史的建造物>
翌朝、歴史的価値を持つという「木造三階建の宿」の案内を所望し、いかにも老舗らしい律儀な番頭さんに丁寧に案内していただいた。
かつてこの旅館は宮津湾のほとりに天橋立と対面するように建てられていた。
それが、京都国体開催による体育施設建設のため前浜が埋め立てられ、一番の魅力である海が見られなくなってしまった。大きな打撃であったに違いないが、歴史的建造物は景色を阻害されたままに残った。
木造三階建の三階部分は大広間になっていて、まるで江戸時代の城郭の広間のよう。
12枚の襖絵は鈴木百年が1年を12の季節として描いたもの、また掛け軸や絵皿も時代物、床の間に置かれた火鉢と弁当箱は宮津藩主が愛用したものだという。
建物の中身はまるっきり文化財。宿泊代以上の付加価値を脳裏に焼き付けて宿を後にした。
<<いよいよ丹後半島>>
< 期 待 >
車のない旅の二日目は、前日とは打って変わった晴天。丹後半島回遊のタクシーをチャーターした。
日本海にこぶしのように丸く突き出す形の丹後半島。その海外線は思いのほか入り組み、しばしば絶妙な景観を眼の前に見せてくれた。冬にしては穏やかな日和で、荒れ狂う白波にはほとんど出くわすこともなかったが、小さな入り江に佇むひなびた漁村はまさしく松本清張か水上勉の世界に通じていた。
<漁村・伊根の舟屋>
伊根湾の舟屋は230軒という小さな集落である。
この何の変哲もない海辺の町が、NHKの連続ドラマ戸田奈穂主演「ええにょぼ」の舞台となったために一躍全国から人を集めるようになった。いまや湾内めぐりの観光船も仕立てられ、春秋の観光シーズンは観光客や釣り人で大渋滞するという。
私にとっては特別な思い入れはなかった。せっかく丹後まで来たのだから足を伸ばしてみようと思ったのだが、思いのほか冬の伊根はすばらしかった。
目の前に小さな青島が集落を波浪から守るかのように横たわり、波穏やかな伊根湾に臨む漁師町、それが伊根。海上に張り出し、階下が船着場で二階が住まいという作りの舟屋は旅行者にとっては、その生活ぶりとともになんともいえない情感を誘う。しかも日本広しといえど、この作りは伊根にしかないという。
< 遊覧船 >
舟屋は海からの眺めが一番ということなので、遊覧船に乗る。2−3日前は時化て運休したといっていたが、冬場は海が荒れ穏やかな湾内でも波浪が高まる。ここで漁獲される魚の中で有名なのが「ぶり」、五島列島・富山湾と並んで国内の三大ぶり漁獲地に名を連ねる。海の色を見るだけで、寒ぶりのおいしさは想像できるというものである。
湾内には養殖用生簀とともに、釣用の大きな生簀が浮かんでいる。ドラム缶ほどの巨大なレンガ色のブイを数十個繋ぎ、その上に木の板を渡し足元の確保をしている。
真冬なのに、防寒服に身を包んだ釣り人が十数人糸を垂れている。あわよくば正月用のぶりをせしめようという魂胆かと邪推し、運転手さんに確認したのだが当たらずとも遠からずのようだ。
車で通ると舟屋の陸側(海とは反対側)が道路になっていて、道を隔てた向かい側にセットでもう一軒普通の家屋が建てられている。代々親と子が住み変わる(譲る)しきたりになっているという。引退したら山側の家に引っ込むという話から舟屋の合理性を感じた。
<新井の千枚田>
運転手さんにあらかじめ調べておいた千枚田を見たいとお願いした。
伊根町からしばらく北に進路を取って、峠を越えると新井(にい)と呼ぶ岬があり、その小さな漁港の急勾配の斜面が千枚田となっている。車のすれ違いが困難なほど狭い雪道を上り詰め、最奥から茫洋とした日本海を眺望した。
「この積雪ですから地元の人しか通りません。」という返事。そのことをわきまえた上でのお願いである。
「お客さんも写真を撮られるんですか?写真家の方はよくいらっしゃいますよ。」
わたしは写真家ではないので生返事。しかしここからの景色は秀逸。田に稲があれば違った景観が得られただろうが、雪景色のほうがずっといい。
若狭湾は冬の群青に染まり、その向こうにポツリポツリと大島・小島の島影を遠望する。足元の千枚田は白いまだらの化粧を施し、その白が太陽の反射でまばゆいばかり。真下は恥ずかしいばかりのつましい漁港で、漁船が十艘ほど係留されている。遠くから一艘、漁を終えた船が戻ってきた。
片手に収まるほどの小さな空間。
来てよかった。
< ザ・タンゴ >
この季節なのに、しかも昨日はあんなに雪が降っていたのに、今日は打って変わった晴天で、これは幸運以外のなにものでもない。
それからの丹後半島冬のドライブは感動もの。絶景が続く。
最北端の経ケ岬、丹後松島などリアス式海岸は荒削りの断崖、奇岩が続き、点在する小島が群青色の海と織りなす景観は真に冬の日本海そのもの。観光客がまったくいない冬だからこそという思いはあった。
しかし、しかしこの後に事件は起きた。
<砂浜でのトラブル>
屏風岩で一休みした後の「立岩」の海岸で、運転手さんは何を思ったか、砂浜の中に勢いよく突っ込んでいった。
一瞬、金沢の「千里浜なぎさハイウエイ」のことが頭をよぎったが、「大丈夫?!」と驚愕の声を発したときにはすでに遅く、ずぶずぶと昨日まで降った雪で柔らかくなった砂の中に車はのめり込んでいった。すぐバックギアに入れて脱出を試みたが後輪駆動の車輪は空転を繰り返すばかりで、車は確実に沈んでいった。
好事魔多し、(これはたいへんだ。)と思ったが口から出た言葉は「こちらは急ぐ旅でもないので気にしないで」と運転手さんに気を遣っていた。
これまで快適に、話も弾んでいただけに(幸せな時間というやつは長く続かないものだ)と改めて感じた。人世も同じで、山があれば谷があり、山高ければ谷もまた深し、幸せと不幸は不連続でやってくる。小さなことであるが典型的な例を見てしまった。うれしくても喜びすぎてはいけない。良いときほど慎重にことを進めるのが肝要なりと、家康のごとく自戒した。
1時間ほど悪戦苦闘したが、結局は地元の車に救援を頼み、ロープでやっと脱出。
これでかにで有名な間人(たいざ)に寄ろうという話もオジャンになった。
「ゆっくり帰りましょう。」と、これ以上ない穏やかな声をかけ、丹後半島を後にした。
<夢の浮橋・続く>
(ページトップへ)
Copyright c2003-6 Skipio all rights reserved