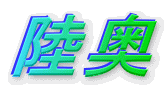![]()
(第四日:角館から山形蔵王へ)

翌朝、5時半に起きだして、朝の温泉に。
山の端から薄日が差し込み幻想的である。
浴衣のまま周囲を散歩する。日陰には雪が残っていて、熊笹も未だ緑を取り戻していない。
地獄谷という地名が多くの温泉場にあるが、この温泉にはあちこちに地獄谷がある。ボコボコと不気味な音を立てて地中から灰色の液体が飛び出してくる。モウモウと湧き上がる湯煙。地球の鼓動が聞こえてくるようだ。鶯の鳴き声が一服の清涼剤となった。
朝食を7時にいただき、8時に黒湯を出発、次の目的地・角館へ。
北海道フリークの真情はさらに北上し、玉川温泉、十和田湖、酸ヶ湯・・・・と足を延ばしたかったのだが、帰りの道程の苦労を思って断念。そろそろ南に進路をとろうということになった。
車の中で、夫婦が同時につぶやいた。「温泉臭いね!」
![]()

< 武家屋敷 >
深い木立と黒い塀の重厚な屋敷が連なる角館は1620年(江戸初期)、この地方を領有していた芦名義勝に開闢の起源がある。
三方を山に囲まれ、前が開けた地形は城下町を形成するのに最適であった。
町の北側に位置する武家町は深い林が覆い静寂感が漂う。一方南の商人町は低い町並みがびっしりと並び喧騒で、好対照をなしている。
< 風 情 >
この町は400年の歴史の中で大きな天変地異や戦災にあわず、開基以来その町並みはほとんど変わっていない。特に80戸が隣り合う武家町は道路の幅から曲がり角ひとつまで昔そのままの姿を残している。角館は、東北の小京都というキャッチフレーズで観光都市を宣言した。
しっとりした風情が漂うこの町が最も賑わうのは、枝垂れ桜が満開の4月下旬。角館の枝垂れ桜は京都三条西家の姫が佐竹家に嫁入りの際、苗木を持参したのが始まりとされる。京都の雅の世界がここにあった。名勝百選の一つ。

残念ながら暖冬の今年は、5月初めでは角館の桜に間に合わなかった。
時刻は午前9時半と、早い。武家屋敷通りを散策する。いくつかの屋敷が内部を公開している。
その一つ、石黒家は佐竹家の家臣で、勘定役。芦名氏断絶後この地に入った佐竹義隣(よしちか)に召抱えられる。屋敷は現存する武家屋敷の中で最も古い。萱葺きの屋根、築山や巨石が配された庭に武士の精神を感じる。贅沢さはない。青柳家、岩橋家、小田野家・・・・・。
この町にはソフィストケイトされた情趣がある。

樺細工は山桜の樹皮をなめして作る伝統工芸であるが、素朴で自然な風合いが暖かい。茶筒一万円なりの創作を目の前で見せてもらった。角館の伝統的銘菓、「唐土庵」の諸越(もろこし)は、小麦粉と砂糖を原料とした甘い菓子だが、高貴な品がある。江戸創業の家伝の味噌を販売する老舗「安藤醸造元」。稲庭うどんの「七代佐藤養助」や秋田比内鶏を食させる料理屋などなど・・・そう比内鶏で「きりたんぽ」など、考えると生唾が出てしまいます。。
 新潮社の創設者である佐藤義亮氏は角館町の出身で、明治37年に新潮社を創設。以来、農村の子供たちに読書をもっとして欲しいという一念で多くの書籍を町に寄贈。記念館が設立された。碑には「出版報国に生涯を捧ぐ 男の本領」とある。
新潮社の創設者である佐藤義亮氏は角館町の出身で、明治37年に新潮社を創設。以来、農村の子供たちに読書をもっとして欲しいという一念で多くの書籍を町に寄贈。記念館が設立された。碑には「出版報国に生涯を捧ぐ 男の本領」とある。そう、忘れていけないのが、黒半被に黒股引に菅の傘とピカピカの人力車。いなせな女性の車夫、いや車婦がおりました。
![]()
< フィナーレ? >
さあ、これで3泊4日の旅はおしまい。あとは東京に帰るだけ。
待てよ。これで終わってしまうのは何か寂しい。休暇はまだある。まだ帰りたくはない。もう一泊しよう。結論が出れば行動は迅速に!
車の中から今晩の宿を探して、携帯作戦開始!ガイドブックにそって電話をかけまくる。東京までの中間点として選んだ裏磐梯のペンションは全滅。連休後半が始まったばかりで当然の成り行きであるが、辛抱強くかけ続ける。あった。あった。20数件目でやっと見つけることができた。
山形蔵王のペンションに一部屋だけキャンセルがあった。
宿を確保できればゆとりができる。あれも見たい、これも見たいの好奇心が頭をもたげて・・・。
「前半に寄れなかった平泉に寄ろう!」奥州平泉は前沢インターからすぐの距離である。
< 奥州平泉 >
「奥の細道」の「平泉」は格調高く、もっとも好きなシーンである。
| 「三代の榮耀一睡の中にして、大門の跡は一里こなたに有。秀衡が跡は田野に成て、金鶏山のみ形を残す。先高舘にのぼれば、北上川南部より流るゝ大河也。衣川は和泉が城を・・・・・・・・・・・・義臣すぐつて此城にこもり、功名一時の叢となる。國破れて山河あり、城春にして草青みたりと、笠打敷て時のうつるまで泪を落し侍りぬ。」 夏草や兵どもが夢の跡 平家全盛の平安後期、奥州藤原清衡は黄金(産出された砂金)をもって中尊寺を開山、華やかな仏教文化を誇った。 (もっとも平家物語は、この陸奥の都を「孔雀の羽をまとった烏(カラス)の都」と描き、平泉の模倣文化を揶揄しているが。) 初代清衡が築き、基衡、秀衡時代に黄金期を迎えた奥州藤原氏も100年の栄華のあと、悲惨な末路をたどることになる。時代は壇ノ浦で平家を破った源氏の世に移っていた。頼朝は奥州征討を敢行。4代泰衡は1189年8月22日(家臣の河田次郎に討たれ)世を去り、ここに奥州藤原氏はあえなく滅亡した・・・。 その滅亡を巡り奥州は多くの逸話を残した。曰く、ジンギスカンになったという義経北行伝説、曰く、マルコポーロの黄金の国ジパング伝説など。 芭蕉翁も先高舘に座って、義経の慙死のことなど陸奥の歴史のあれこれを深く考えたに違いない。 |
この平泉行きは、結果として無駄な時間になってしまった。
< 祭 >
この日は藤原氏の中尊寺開山1150年にあたる祭礼の真只中で、街道筋は大渋滞。駐車場は満杯で車は身動きが取れない。しかも今まさに、何か大きなメーンイベントが行われようとしている。そんな雰囲気の高まりの中に迷い込んでしまったわけだが、なすすべもなく、混雑を避け農面道路を迂回して古川へ。
後で調べた結果、今まさに「源義経公・東下り」の行列が現れんとする時であった。
すべてをあきらめ「早めに蔵王に行こう。」と。
![]()
<蔵王・坊の平>
 山形に戻ってきた。
山形に戻ってきた。
山形蔵王インターで下り西蔵王高原ラインを上る。上り下りの曲がりくねった道は遠かった。四苦八苦しながら、やっとの思いで「坊平」に辿りついた時、太陽はすでに西の山の端から消えようとしていた。山の夕暮れは寒い。
「いらっしゃい。たいへんでしたでしょう。」と笑顔で迎えてくれたペンションの暖かさが嬉しかった。
 < 山 >
< 山 >ペンション「アルム」は昭和49年オープンというからペンションブームが始まる前、はしりの頃の設立である。オーナー夫婦は二人とも山好き。早稲田を中退した鈴木洋吉さんは昭和20年生まれ。八ヶ岳、吾妻山など山暮らし10余年のあとペンション開業。山が好きで、学問なんて馬鹿らしくなって、学校も辞めてしまったのでしょう。
こういう人生は本当にうらやましいが、この方、なんと漱石とも親交があった鈴木三重吉氏のお孫さんという。
奥さんは人形劇団出身という変わった経歴の持ち主。陶器作りやパッチワークが趣味で、実益も兼ね、ライフワークとして取り組んでいらっしゃる。「仙人がま」と称する陶芸窯の主催者で、希望があれば陶芸教室を開いてくれる。
夕食は久しぶりの洋食。
和室・畳・お膳の食事から、ナイフとフォークの世界へ。
風呂上りのビールで乾杯し、赤ワインのボトルをほぼ一人で開けてしまった後、ウイスキーにも手を出した。「お強いですね。」とほめられたのか、あきれられたのか。
気持ちの良い夜であった。
<続く>
Copyright c2003-6 Skipio all rights reserved