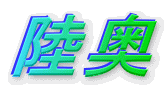<プロローグ>
××歳という人生のひとつの転機を迎え、気分転換も兼ね初めての思い切った長旅を敢行した。事前に十分にかの地のことどもを調査し、満を持しての旅であり、どのようなことに相成りますやら・・・・?
岩手県出身の直木賞作家・高橋克彦氏は「説明できない歴史と東日本のたび」でこう書いている。
「東北の古代をテーマに物語を作ろうとするとき、いつも不安を覚えるのは資料の少なさだ。断じて歴史がなかったわけではない。歴史が勝者によって意図的に抹殺されてしまったのだ。東北の歴史はほとんどが伝承や民話の中に埋められてしまっている。・・・・・・・滅ぼされた文化がいかに豊潤で純粋で先進性にとんでいたことか。訪れた人々は美しい自然の景色の中にはるか古代の東北文明のオーラを無意識に感じ取っているのではなかろうか。」と。
まさに東北文明への旅である。
![]()
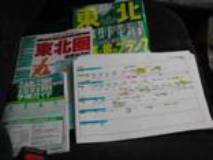 <懐かしき山形>
<懐かしき山形>かつて20年を越える昔、毎年春先に山形の町や村を縦走した時代があった。数年間、同じ季節に同じ町々をたどったという記憶がある。仕事のスケジュールは目一杯で余裕もなく、津々浦々を、じゅうたん爆撃さながらに忙しく回った。

田園に苗代がはられ田植えが始まっていた。行く先々で歓迎を受け、山菜の王様「たらの芽」「こごみ」「やまうど」「ぜんまい」など新鮮な山菜のてんぷらや煮つけをたっぷりご馳走になった。
山々には雪が残り里の河川には例外なく雪解け水があふれていた。そんな懐かしい思い出を胸に、東北の第一歩が山形から始まった。

< 山寺にて >
将棋のこま日本一の天童から山道をしばらく走ると山寺に着く。
観光地化されているのか、おばさんたちが駐車料金500円也を競って、道の端で大声をあげて客を誘う。歓楽街の酔客を当て込んだ客引きの様子に似て、興ざめである。
わたしは参道に一番近いところに車を止めた。
 登り口を尋ねた土産物屋の女将さんが「だんなさん、そばでも食べていってくださいな。」と引き止める。返事をしないでいると、「そばは嫌いですか?」と勝手に決めつけられてしまった。話しついでにカメラを差し出して記念写真をお願いする。デジカメにもかかわらずファインダーをじっくりと覗いて、束の間の思案の後でおもむろにシャッターを切った。本当に撮れているのか不安顔をしている。「大丈夫ですよ、ほれっ!」と小さなビュアで見せてあげると、納得顔で「あれ、まあ!」と感心と驚きの眼。多少の手ぶれは我慢我慢。
登り口を尋ねた土産物屋の女将さんが「だんなさん、そばでも食べていってくださいな。」と引き止める。返事をしないでいると、「そばは嫌いですか?」と勝手に決めつけられてしまった。話しついでにカメラを差し出して記念写真をお願いする。デジカメにもかかわらずファインダーをじっくりと覗いて、束の間の思案の後でおもむろにシャッターを切った。本当に撮れているのか不安顔をしている。「大丈夫ですよ、ほれっ!」と小さなビュアで見せてあげると、納得顔で「あれ、まあ!」と感心と驚きの眼。多少の手ぶれは我慢我慢。
< 輪 廻 >
さて、わたしは迷うことなく宝珠山立石寺・山寺を上り始める。
 赤い風車が参道の石碑の脇に置かれている。色のコントラストが際立っていて、よく目立つ。何だろうと、名物の「力こんにゃく」を売っている茶店のおばさんに尋ねてみた。
赤い風車が参道の石碑の脇に置かれている。色のコントラストが際立っていて、よく目立つ。何だろうと、名物の「力こんにゃく」を売っている茶店のおばさんに尋ねてみた。
「あれは水子供養の風車なんですよ。」と、想像していた通りの北国なまりのことばが返ってきた。
風車の回るさまは、人の世の輪廻の世界に似て、複雑な思いが交錯する。
<曽良とともに>
 山寺といえば芭蕉「奥の細道」の傑作が残る。
山寺といえば芭蕉「奥の細道」の傑作が残る。
閑かさや
岩にしみいる 蝉の声
「奥の細道」中もっとも優れた句の一つ。初案は、「山寺や石にしみつく蝉の聲」。後に「さびしさや岩にしみ込む蝉の聲」となり、最終的に現在のかたちに納まった。最初の句が徐々に深められ現句に昇華された。
芭蕉が弟子の河合曽良とともに山寺を訪れたのは元禄2年(1689年)の夏、新暦7月13日午後4時ごろ。「尾花沢」逗留で世話になった紅花商の鈴木清風の勧めによって予定外の訪問であった。
<鈴木清風>
少し寄り道して鈴木清風のこと。
当時尾花沢一帯は全国一の紅花の産地。働き盛りの清風は芭蕉より7歳、曾良より2歳年下の39歳、この季節は紅花の商いでもっとも多忙な時期、芭蕉師弟の世話は十分できなかった。それでも芭蕉が満足をもって10日以上滞在したところをみると、それなりの接待をしたと考えられる。
紅花は都で暮らす女性には欠かせない化粧の道具。この地域で生産された紅花は「大石田」(後述)から最上川を下り、河口の酒田から北廻り船で敦賀に荷揚げされ、今度は陸路琵琶湖へ、さらに海路で京都に運ばれた。
清風は晩年商人として大成功を収め、江戸吉原の高尾大夫を大名と競ったとも伝えられている。
さて話は山寺に戻る。
| 「岩上の院々扉を閉めて、物の音きこえず。岸をめぐり、岩を這いて、仏閣を拝し、佳景寂寞として心澄み行くのみおぼゆ。」 |
現代の自称・芭蕉研究家の文化人たちは必ずここを訪れ、資料集めに余念がない。
 しかし、ここ立石寺山寺は芭蕉よりずっと古い歴史を有する。平安の昔、西暦860年に天台宗三代座主・慈覚大師が開山した名刹であり、根本中堂は比叡山延暦寺に倣って創建したという。鎌倉時代には三百余の寺坊に千人を超える修行僧が居住し、東北山岳仏教の中心地として盛況を極めた。没落と復活の繰り返しで今日に至る。
しかし、ここ立石寺山寺は芭蕉よりずっと古い歴史を有する。平安の昔、西暦860年に天台宗三代座主・慈覚大師が開山した名刹であり、根本中堂は比叡山延暦寺に倣って創建したという。鎌倉時代には三百余の寺坊に千人を超える修行僧が居住し、東北山岳仏教の中心地として盛況を極めた。没落と復活の繰り返しで今日に至る。
みちのくの 仏の山の こごしこごし
岩秀に立ちて 汗ふきにけり
斉藤茂吉
 < 静と汗 >
< 静と汗 >
山寺は全体が岩山である。修行僧は険しい岩山の上り下りの苦行の中で精神を鍛えた。足を踏み外し転げ落ちた若い修行僧が毎年何人もいたそうだ。まさに命がけの修行で、石段の奥に、刻まれた文字も読み取れない苔むした石のあるのは、志し半で亡くなった僧の碑か。
今は足元も整備され、快適な山歩きができる。運動不足の中年諸氏にはちょっと厳しいかもしれないが・・・芭蕉翁のいう閑かさを堪能できる。

 頂上に近く見晴台がある。ここから眼下に広がる茫洋とした眺めは一見の価値がある。奥深い山の底を流れる芹沢川、川沿いに寄り添って張り付くように並ぶちいさな集落。仙山線を走る二両連結のディーゼル機関車。筆舌に尽くしがたし。
頂上に近く見晴台がある。ここから眼下に広がる茫洋とした眺めは一見の価値がある。奥深い山の底を流れる芹沢川、川沿いに寄り添って張り付くように並ぶちいさな集落。仙山線を走る二両連結のディーゼル機関車。筆舌に尽くしがたし。
わたしは、かけるように登り、かけるように降りたが、さすがに汗が噴出した。
芭蕉記念館に隣接する後藤美術館では、なぜか、バルビゾン派ミレー・コロー・クールベの特別展を開催していた。
![]()
<あらきそば>
< そば街道 >
山形市の北方天童市に隣接する村山市は最上川の流域に広がる田園地帯。最近、その最上川三難所(後述=奥の細道)に「そば街道」という名所ができた。
本格的手打ちそば14店が、腕を競う。店舗ごとにそれぞれ特徴を持ち、打ち立ての香り高い味覚を提供してくれる。
もともと良質な蕎麦と自然水が豊富に取れる土地柄、蕎麦どころ山形の中でもそのうまさは群を抜く。
本日の昼食は十四番店「あらきそば」に決めていた。
 囲炉裏を構える薄暗い座敷の雰囲気と茅葺きの外観は幾年月まったく変わっていない。
囲炉裏を構える薄暗い座敷の雰囲気と茅葺きの外観は幾年月まったく変わっていない。
聞けば「大正9年から店を開いている」というからよほど古い歴史がある。
「板そば」といい、長方形の板の上に盛り付けてそばが出てくる。新潟のへぎそばに似ているのは、何かのつながりがあるに違いない。量は多い。
少な目の「うす毛利」(七百円也)とにしんの味噌煮を頼む。かつて昼食に立ち寄ったときの記憶では、近隣の顧客は大盛りの「昔毛利」を頼み、残したそばをあらかじめ用意したどんぶりに入れて持ち帰っていた。当時まだ若かったわたしは「昔毛利」をぺろりと平らげてしまったものだが。
 出てきたのは腰の強い田舎そば。そばつゆが絡みにくいが、その分そば本来の甘味をよく噛んで味わうことができる。つるつると、のど越しを味わうそばとは一線を画する。
出てきたのは腰の強い田舎そば。そばつゆが絡みにくいが、その分そば本来の甘味をよく噛んで味わうことができる。つるつると、のど越しを味わうそばとは一線を画する。
つなぎは使用せず、そば粉100%の手打ちそば。秋口に取れた蕎麦を低温倉庫で貯蔵し、毎日その日の分を打つという。
「昔、私のおじいさんのころは石臼で引いていたが、最近は機械でやっている。」と若女将は感慨深げである。
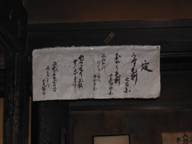
< 若女将 >
私が「昭和57年ごろですから、もう20年ほど昔、一度仕事の途中におじゃましたことがある。昔とまったく変わっていませんね。」と懐かしく話しかけると、女将さんは「じゃあ、私はまだ女学生でしたね。ありがとうございます。」と丁寧な返事が返ってきた。
思い上がることなく一所懸命伝統を守ろうとしている。この店の商売繁盛は間違いない。
母なる河よ最上川 辛夷の花 白くかおり
雪解けの水 岸を洗う 真壁 仁
< 最上川 >
「あらきそば」にはいる直前から5月の雨が降り始めていた。
 食事を終えた道すがら、大石田町を流れる最上川の水車を撮ろうと駐車場に車をいれた。最上川は普段から満々と水をたたえ雄大に流れているが、この雨のためいっそう水かさが増えたような気がした。
食事を終えた道すがら、大石田町を流れる最上川の水車を撮ろうと駐車場に車をいれた。最上川は普段から満々と水をたたえ雄大に流れているが、この雨のためいっそう水かさが増えたような気がした。
| 奥の細道は「最上川は、みちのくより出て、山形を水上とす。碁点、はやぶさなどおそろしき難所あり。板敷山の北を流れて、果ては酒田の海に入る。左右山覆い、茂みの中に船を下す。これに稲つみたるをや、いな船といふならし。白糸の瀧は青葉の隙々に落ちて、仙人堂、岸に臨みて立つ。水みなぎつて舟あやうし。」とあり、名句が生まれた。 五月雨を あつめて早し 最上川 |

< 推 薦 >
大河の光景を何箇所か撮って戻ると、軽4輪トラックに農業肥料を積んだ地元の年輩のおじさんが何か言いたげに雨の中を待っていた。
「多摩ナンバーですかいの。東京からですの?連休で里に帰っておいでです?だいぶ時間かかったでっしょ。」と愛想のよいことばが続く。適当に話をはぐらかせていたが、「今晩はどちらに泊りなさるの?」「銀山温泉がこのへんではいいですの。」とこちらが銀山の名前を出す前から今宵の宿を推薦してくれた。まるでこの言葉を伝えたいがために待っていたかのようであり、銀山温泉が郷土の誇りというようにも感じ、同時に言葉の端々に土地の人のまことの優しさを感じたのである。
< 大石田 >
さて、宿に入るには時間が早い。大石田の駅を確認するために、春雨の中、村山盆地を徘徊するが、方角を失いだいぶ手間取ってしまった。
午後3時40分大石田駅にやっと到着。
東京「有明」で開催されている試合のために遅れて到着するママさんの、到着後のバスの時間を調べたが、5時にて今宵の宿・銀山行きのバスは終了してしまう。
ママさんの到着は午後7時29分。さて、どうしたものか。何とか一人で来させる算段をしてみたのだが、どうもタクシー以外に手はなさそうである。
仕方ない。食事の時間を遅らせてもらって私が迎えに行こう、と結論を出す。
結果的に夕食の時間を2時間も遅らせて旅館の主人に迷惑をかけることになってしまった。
![]()
<銀山温泉>
< 大正ロマン >
湯煙と深山の気配の中、銀山温泉は予想していたとおり、雨が情緒を盛り上げて迎えてくれた。
小さな峠に上り詰め、下を眺めた瞬間、谷の底に小さな温泉街が・・・・。
ひっそりと歴史の向こうから出てきたような・・・・。
 特徴のある木造建築で、三層、四層に重なる旅籠の屋根の一つ一つに銀山の歴史が宿っている。大正2年創建当時の、良き大正ロマンの面影を偲ぶことができる。
特徴のある木造建築で、三層、四層に重なる旅籠の屋根の一つ一つに銀山の歴史が宿っている。大正2年創建当時の、良き大正ロマンの面影を偲ぶことができる。
派手なみやげもの屋などはない。つましく、そっと、何かに耐えながら生きてきたという風情に感じられた。
開山500年の歴史を紐解いてみると、かつて短い間、銀鉱が栄えていた時があった。元禄年間の大崩落により廃鉱を余儀なくされたようであるが、その時代、鉱夫たちは毎日銀山の温泉につかりその日の疲れを癒し、地酒を酌み交わした。かれらは何を思いかつ何を語り合ったのだろうか。
< 雨 >
小さな山奥である。
温泉街への車の乗り入れを禁止し、峠の上から歩いて降りる。そこに清流・銀山川を挟んで10数軒の宿がひっそりと軒を並べている。全部の宿の名前を書き並べても数行で足りる。
居並ぶ旅館は数層の屋根を持つ同じような木造の建築様式で建てられており、一軒一軒が屋号とは別に人名を大きく表示している。たとえば「能登屋」には「木戸佐左ヱ門」と。
 右手の宿に入るためには銀山川をわたる木橋がかかっている。一の橋、二の橋、三の橋・・・というように。この橋は人が歩くとぎしぎしと音をたて、途中、板がめくれているところもあり、なんとなく危険な感じがする。
右手の宿に入るためには銀山川をわたる木橋がかかっている。一の橋、二の橋、三の橋・・・というように。この橋は人が歩くとぎしぎしと音をたて、途中、板がめくれているところもあり、なんとなく危険な感じがする。
温泉街を200mほど中に進めばそこがもう道の行き止まりで、高さ22mの白銀の滝が轟音を立てて流れ落ちていた。そこから廃鉱につながる山道が始まる。これが銀山温泉のすべてである。
しかし、この小さな温泉街がたまらなく魅力的なのである。温泉全体の統一された景観が見事で、全国から人を集めている。そういえば「おしん」の母はここで若い時代を過ごした。
銀山温泉は川沿いに湧出した源泉をそのまま内湯に取り込んでいる。温泉の発見は江戸初期。出羽の名湯として名高い湯は、細かな湯の花が混じった乳白色。湯温は熱い。水でうすめて入った。泉質は含食塩硫化水素高温泉というのだそうだ。
<浴衣に丹前>
夕食は、川を見下ろす二階の部屋で、黒塗りの箱膳を向かい合っていただく。湯煙が窓の外にゆらゆらと揺れている。酒がおいしい。早春の奥山の料理である。
鮎の塩焼き、この日山から採ってきたという山菜のてんぷらとおひたし、さしみはサーモンとほたて、牛肉とたまねぎ・しいたけのほう葉焼き、たけのことこんにゃくの煮物、おきゅうとのような柔らかな切り物。ごはんは山形庄内米である。こちらの時間に合わせて暖かい食事を用意してくれたのがうれしい。素材に鮮度があるからだろうが、期待していた水準をはるかに越えている。
酒がすすむ。 ほてった顔を覚ますため、窓を開けて外の空気に触れる。
ほてった顔を覚ますため、窓を開けて外の空気に触れる。
銀山の情緒そのものが窓の外にあった。
雨に煙る温泉街とガス燈の光。耳に入るのは流れ下る川の音。
しばし呆然、うっとりと。銀山には雨が似合っている。
柴田屋は客室5部屋の小さな宿である。まだ若いご夫婦二人で旅館を切り盛りしている。
宿の施設は老朽化していて、廊下もみしみしと音を立て、引き戸の立て付けも悪かったりしたが、思い直せばこれも自然で情緒あふれる世界。
われわれが宿泊した日は二人だけの客であったが、ご夫妻の親切で心のこもった接客の気持ちを十二分に感じ、銀山温泉の好印象が倍加した。
翌朝8時、宿の主人に記念写真を撮ってもらい銀山温泉に別れを告げた。
<続く>
![]()
![]()
![]() (陸奥TOPに戻る)
(陸奥TOPに戻る)
Copyright c2003-6 Skipio all rights reserved