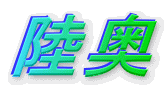![]()
�i��O���@�{�Â����茧�����f�@��������ցj
���O���C�ݏ�y���l��

���@�C���ց@��
�@���N�����A�����E��y���l����8�F40�o���̃��A�X���C�݂߂���̊ό��D�u�����ہv�ɏ��B
�@�u�����͔g����������A�C�͔��͂������Ă�����B�v�ƁA��ӂ������ɂ����A�����ɂ��l�̂悳�����Ȓ��ԏ�̂��������������ȏ���Y���Đ������Ă��ꂽ�B
�@�u���������������͂��������낤�B�v�ƋC�������V�Ԃ点�邱�Ƃ������B
�@�D�͒荏�ʂ�A�^���ȑ�C���ɏo�q�����B

�@�����ɂ����߂̑�Q���ǂ������Ă���B��������ƎO���̌i�ς��ώ@����O�ɁA�O���̃V���[���n�܂��Ă��܂����B
�@�a�̊��p�����܂�Łu���痈����v�Ƙr��L���ƁA�J���������͎w�̂�����������ɒD���Ă����B�����q���������ĊC�ɗ��Ƃ��Ă��܂����a�ǂ����A���܂��������ɋ��݁A�E���グ��B���ʂ��Ȃ��B�������ǂ����̃J�����̂悤�ɂԂ�Ԃ�Ƒ��炸�X�}�[�g�ł���B���炭�J�����ƋY���B
���@�g�ӂ��ā@��
�@�������ɎO���C�ݍ��������̌i�ςł���B���E��₪�����B�u����ł͌����Ȃ��R�̗��N�ƐN�H���͂�����Ɩڂ̑O�Ɍ�����B�����̊�ɍr�X�����g���P��������B�ӂ��U��g��10���[�g�������ˏオ���Ă��Ԃ������B
�@�V�R�L�O���u���������v�����30���[�g�����̍����ɐ�������яオ��B�傫�Ȋό��D�����A�R�ɋ߂��Ƃ���ł͔g�̒��˕Ԃ�ɑ傫���h���B40���قǂ̍q�H�ł��������A���͂��猾���Γ��{�O�i�E�����̌i�ς���ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��B
���Ɋy��y��

�@���͐́A�w������A�O���C�݂̂��܂�̔������ɁA���Ȃ̏����ɐ�]���Ⴂ���������F�l�������B�V�˂ł��������A����ł������B�ӂƎv���o�����B
�@�r�ꂽ�C������Â߂邽�߂ɁA�R�[�q�[����t�B�����A�����Ɍ������ďo�����B
�������҂��҂��Ɂ�
 �@��茧�̒��S�Ƃ������A�V�������ʂ��č��Ⓦ�k�n������̓s��ƂȂ��������s�B��Ɋ��R�Ƃ����G����A�s���𗬂�钆�Ð쉈���ɂ͌Â��ǂ��ʉe���c�����������_�݂���B���͂ɂ͖����������A�l�G�܁X�A���R�i�ł���B
�@��茧�̒��S�Ƃ������A�V�������ʂ��č��Ⓦ�k�n������̓s��ƂȂ��������s�B��Ɋ��R�Ƃ����G����A�s���𗬂�钆�Ð쉈���ɂ͌Â��ǂ��ʉe���c�����������_�݂���B���͂ɂ͖����������A�l�G�܁X�A���R�i�ł���B�@���傤�ǒ��H�̎��ԁB
�@�����ŐH���Ƃ����A����Ɨ�˂Ƃ��Ⴖ��˂��L���B
 �@����͗������O����A�����C���^�[�߂��́u�҂��҂����v�̗�˂ɒ��킷�邱�ƂɌ��߂Ă����B�����͏ē��n�̃��X�g�����Ȃ̂ŁA�u�v���Ԃ�ɂ������B�v�Ƃ������D���̂܂܂���̗v�]�����ďē��Z�b�g���ꏏ�ɒ�������B
�@����͗������O����A�����C���^�[�߂��́u�҂��҂����v�̗�˂ɒ��킷�邱�ƂɌ��߂Ă����B�����͏ē��n�̃��X�g�����Ȃ̂ŁA�u�v���Ԃ�ɂ������B�v�Ƃ������D���̂܂܂���̗v�]�����ďē��Z�b�g���ꏏ�ɒ�������B�@�����Ȋ��z�͓�d�ہB�J���r�E�^���̏ē��͏_�炩�������ւ����������B���A�ŐH����ƃW���[�V�[�ȊÂ��������ɍL����A�������ɁB���������̂���Ђ��Ɨ₽����˂Ƃ̑������҂���ŁA���H�̑I���Ƃ��ẮA���[�Y�i�u���Ȃ��l�i�Ƃ��킹�đ吳���B
�@�L���`�ƍ������s���J���̃X�[�v���c�������݊����Ă��܂����B
�@�A�x�̉Ƒ��A�ꂪ�����A�X���͑���킢�B15���قǑ҂����ꂽ���A�㖡�̂悳�ɁA�҂����ꂽ���ƂȂǂ�������Y��Ă��܂����܂܂���Ƃ킽���ł��B��˂͕Ă̂Ƃ�ɂ��������n��ɓ`���~�̗����ŁA�˂͂��Ε��E�ł�Ղ�E�����������グ�č��B�X�[�v�͂܂�₩�ȍ����(�L�W)�̂����`������B���̑��������Q�ŁA�����l�C�Ă���B
���@��@�ˁ@��
�@���āA������˂̃��[�c�͒��N�����̕���i�s���������j�B
�@���܂�f�v���œ��{�l�̍��݂̓I�ƂȂ��Ă���k���N�̎�s�ł��邪�A�H�̐��E�͕ʂ̘b�B����Ɛ����͋C���Ă���A������ӂ邳�ƂɎ������l���̋����Â�ō���Ă݂��̂�������˂̔��˂Ƃ����B
�@�֑��B�����̍��̂��ǂ�ł��Ǝ����Ƃ��낪����Ǝv���B���ǂ����˂��̂���j�����̗����A���n���̗͎d���͓��R�j�̎d���B��˂�������Ƒ���q�������̂��߂ɍ���Ă��܂����B
�@���Ȃ��������ς��ɂ��Đ����ɕʂ��������B
�@���炭����Ɓu�����_��v�̈ē����o��B����46�����E�܁B25���قǂœ����B
![]()
�����R��
�@�����_�ꂩ��͊��R���傫��������B�[�c�v��̓��{�S���R�͎��̂悤�Ɍ���Ă���B�@�u��茧���������̐l�ށA�����̐��_�̏�Ɋ��R�����e�����ɂ͂����Ȃ��������낤�B�Y�̂ɂ��ďd���A���k�l�̓y�������ے�����悤�ȎR�ł���B���Ă̖��吷�����w�̏��N�����́A��������Ȃ���w�т��V�B�ΐ������̈�l�ł������B��N�����̐����𑗂����ނ̊��ɂ́A�����k���̊ݕӂ���]���R�̑��݂��������ɈႢ�Ȃ��B�v
�@�ӂ邳�Ƃ̎R�Ɍ��Ђ�
�@���ӂ��ƂȂ�
�@�ӂ邳�Ƃ̎R�͂��肪��������

�������_�ꁄ
�@���܂���u�����h�ɑ�������i�̃g�b�v�u�����h�ł���u�����v�B���̖��O�̐V�N���ɖ�����āA�̖q��̃C���[�W���v���`���ĖK�₵���B| �@���̒n�̗��j�́A����24�N�O�H�̊���V���E�����A�L��ȉΎR�D�̌���ɊJ���̌L����ꂽ���ƂɎn�܂�B�����̒~����̂���A�����̎s�́A�`�[�Y�E�o�^�[�̐��Y�̔��Ȃǂֈڍs���Ă������A���Ƃ̊�b�͂��ׂĖ�������ɍ��ꂽ�B |
�@�Ȃ�ƍ����A�������Ƃ��i�ٔ����Ƌ����œW�J����Ă���Ƃ����B�̔��`���l���̂��Ƃ��l����A���ɓ����ɂ��Ȃ��Ă���B
���@�܂��@��
�@������Ƒ傫���L����̔_��B�w�i�ɂ͂��܂��Ⴊ�c����R���Y��Ȏp�ŋ������Ă���B���ʐ�3000ha�ƁA�ƂĂ��Ȃ��傫���B
�@�����_��u�܂��Ή��v�͎��R�����ς��������ς��̎q���̗V�я�Ƃ�����ہB
�@�r�E�n�ȂǓ��������ƋY�ꂽ��n�C�L���O�����肨�ٓ���H�ׂ���A���R�Ɏ���đ厩�R�i�ł���B��Ԉ�ۂɎc�������̂́u���F�[���F�[�v�Ɩ��r�̐��B
�@�q���̂���A���������̎���ɎR�r�����炳��Ă����B���̖����͓���I�Ȃ��̂ł��������A�ˑR�߂��Ŗ���Ă��܂��Ƌ����Ă��܂����B����Ȃ��Ƃɋ��������ɋ����Ă���̂����E�E�E�E�B
 �@�r�ɂ̒��ŁA�т�����ꂽ����ȗr�������Q����Ȃ��Ă������A�����ňꖇ�ł��M���z�C�̂��̓��́A���������A�K�������ł������B���ꂪ���R�̐ۗ��Ƃ�������낤���B
�@�r�ɂ̒��ŁA�т�����ꂽ����ȗr�������Q����Ȃ��Ă������A�����ňꖇ�ł��M���z�C�̂��̓��́A���������A�K�������ł������B���ꂪ���R�̐ۗ��Ƃ�������낤���B�@����Ȓ��Ŏq�r���A�ۗ����ĉ��������B�����₩�A�]���A���a�A����Ȍ��t���҂����肷����i�ł����B�����̐l�C���[������A�ԈႢ�Ȃ��q�r����Ԃł��傤�B
 �@�����āA���܂�u�����h�i�ƂȂ����u�`�[�Y�E�o�^�[�v��u���v�ȂǓ����i�����y�Y�ɁE�E�E�B
�@�����āA���܂�u�����h�i�ƂȂ����u�`�[�Y�E�o�^�[�v��u���v�ȂǓ����i�����y�Y�ɁE�E�E�B�@��������R�����ɏ������������ΖԒ������������ɁB�����͂��킽����������}���܂����B
�@���Ήw���o�R���ďH�c�X��46��������H�c��ցB
�@���̂�����͗ǎ��̉���̕�ɂŁA�������E�E�E�E�B�����A���̑O�Ɂu�����P�v��q�炵�����E�E�E�B
![]()
�@���낵���������g���l������ƁA�����͏H�c���B����341���i�H���Ƃ�A�k�シ�邱��10�����Ő��[423.4���[�g���Ɠ��{����ւ��c����ɒ����B
�@�܂��t�̏��߁B�ɐl�̋C�z�����Ȃ��B���X�Ƃ��Ă���B

�@�~��ɋ߂Â����Ƃ��ł��Ȃ����������y�̂������낤���H����Ƃ��ߊ�肪���������������̂������낤���H
�@�`���̔������C�q�́A�i���̎Ⴓ�Ɣ��e��ۂ������Ɗω��l�ɕS���S��̊�������A���̂ɕϐg���ΐ_�ɂȂ����Ɠ`������B
���@�ǁ@���@��
�@���́u�����v�́A���t�̗[��ꎞ�A�_�炩�ȕ��������āA�̐��݂Ƀu�����Y�̔��������̂�I�ɂ��Ă����B
�@���m�ɂ͑��2���[�g���A���������h�d�グ�Ƃ����炵���B��ҏM�z�ە����́u�R�̒��Ɉ�������������₩�ȉ����̎p�v��������B�ڗ��F�̌Ώ�ɐ_�X�����A��������㵒p���܂�Řȗ����Ă���B
�@�`���̒��ł́A�~�A���Y���̑��Y���c��ɂ���ė���B�u��l�ŕ�炷����g�����A���������ēc��͓~�����邱�Ƃ��Ȃ��v�̂��������B
 �@�����͎���20�`��������1���B䩗m����ł������B
�@�����͎���20�`��������1���B䩗m����ł������B�@�A�r�ɂ��Ă���A�H�c�o�g�̈��݉��̂��v�w�Ƃ̉�b�B��l���������낦�Ęb���Ă��ꂽ�B
�@�u�c��͑D�ɏ���āA��������͂�����̂���ԁB���̐_�邳���悭�킩��܂���B���͂��Ђ������ĉ������ȁB�c�O�ł����I�v
�@�������B������v���ŎԂ𑖂点��B���A�c����������o�āA�������u�߂̓�����v�ցB
�@���̕ӂ́u�\�a�c���������������v�̍œ�[�Ɉʒu����B
![]()
�@�铒�̒��̔铒�ƌĂ�Ă���B�H�c���c��̖k���A�����R�̎R���A��B��ɉ��������������͐Â��Ȃ������܂���������B�̗ǂ�������{��̉���ƁA�铒���D�Ƃ��獂���]�����Ă���B
�@�������͂��̒n��ɂ��鉷��̑��̂ŁA��̓I�ɂ́u�߂̓������v�u���T������v�u�劘����v�u�I�ꉷ��v�u���Z����v�u��������v�̂U�����w���B
�u���Z����v�Ɓu��������v�͗אڂ��Ă��邪�A����5�`�l���ɓ_�݂��Ă���B
���@�����@��


�@�킽�������̂��̓��̏h�͍�������B
�@���ܑ��̂�������������J���ēo���Ă����B���₪�����ɂ��铒�C�������܂�B��Ԑl�C�́u�߂̓��v�ɗ�����������A�c�O�Ȃ���O�����������̌ߌ�5���ɊԂɍ��킸�B������߂č���������������A�����C�ɂȂ����̂��߂̓����ΎG�ȕ��͋C�B�����낤�H��������l���W�߂����Ă���̂ł͂Ȃ��낤���H���Ǝ�`�H�铒���H
���@���q�H�@��
�@��������͓������̍ŏ㗬�ɂ���A���̌���͐�B��̎x��������ɂ���B
�@���̍s���~�܂�̒��ԏꂩ��A�}�ȎR�����~���Ɗ������������ڂɓ���B���Ƃ̗��l���Z��ł���悤�Ȑ̂���̉Ɖ��ł���B
 �@�܂܂���͐�ɎԂ���~��āA�d���ו��������l�Ő�ɍs���Ă��܂����B
�@�܂܂���͐�ɎԂ���~��āA�d���ו��������l�Ő�ɍs���Ă��܂����B�@�킽�����U�蕪���ו��ŋ}�ȍ⓹���~���B
�@���āA�Â��������A���畘���̌����ɕ���ŁA���đ��������炵���ؑ��̉Ɖ����s�A���ɑ����B�ǂ�����h�ɓ����Ă����̂��킩��Ȃ��āA����낫��낵�Ă���ƁA���l�����o�R�q�̈�l���u��t�͂�����ł���I�v�Ɛe�Ɉē����Ă��ꂽ�B
 �@�Ƃ��낪�A�ǂ��ɂ���ɍs�����܂܂����Ȃ�!!
�@�Ƃ��낪�A�ǂ��ɂ���ɍs�����܂܂����Ȃ�!!�@�ǂ������q�ɂȂ��Ă��܂����炵���B�u�Ђ���Ƃ��ĊR���ɓ]���E�E�E�H�v�ƁA����₠���Ă͂Ȃ�Ȃ��s���������悬��B
�@�ו����A�h�̐l�Ɉē����ꂽ���d���ЂƂ̕����ɒu���āA�{���ɏo��B
�@�h�Ƃ͔��Α��̍���~��n�߂�ƁA����������ו����������܂܂��͂��͂������Ȃ���o���Ă����B���Ⴂ���āA��O�̑��Z����ɍs���Ă��܂����炵���B
![]()
�@�ŋ߂͔铒�u�[���ŁA��҂����|�I�ɑ����B�������j���̃J�b�v���ł���B
�@�Ⴂ�l�Ɖ���͌��т��Ȃ��̂��������Ȃ̂ł���B
�@���N�̂��߂Ƃ������̂ł͂Ȃ��A���W���[�����Ă���B�}�X�R�~�̉e�����낤���B
�@����ȎႢ�l�������O�������ł���Ă���B�ޏ������̓J�����Ў�ɍ����̘I�V�X�Ɣ`���Ă����B�ꏏ�ɓ���悢�̂ɂƁA�v���̂����A�������ɒ��Ԃ̂�������j�������Ă��鍬���I�V�ɓ���E�C�͂Ȃ��悤�ł���B�����ɂ͏�����p�̘I�V���C���p�ӂ���Ă��āA������ɐZ�����Ă���l�q�B

�@�������̎�����̊��̂�������������������Ɠ��C�������Ă���B��D���Ȑ̉�����������̘I�V�ł���B���D�̉��͉���ɐ���č����肵�Ă���B
�@��������̓��͔��������������f��Ǝ_�������B���ɂȂ߂炩�Ɋ�����B
�@���܂ŐZ�����Ă������Ƃ��炾�����߂�B���̔�ꂪ�������ɔ����Ă����B�����͔M�����Ȃ��ʂ邭���Ȃ��A�K���ɒ������Ă���B�z�Ɋ����������牏�ɍ����āA��₷�B�����Ă܂��Z����B������J��Ԃ��B

�@���낻��[�H�̎��Ԃł���B�H�������������B�܂���Ԃ̉��B����̋�ɂ͎R�ɍ������āA�m���Ɏ��̓��B�Ȃ`�ɁA�H�c�炵����낤�ǂ������܂��Ă��������B�����Ȃ͊⋛���Ă��Ă��ꂽ�B�n�̂��Ђ����A�C�J�̃E�j�a���A�֎q�Ă��A���q�����A���V���͂��Ԃ肪�����B���܂��`�ɂ͂�����H�c���Y�E�{���E�E�E�B
�@�Ăǂ��낾�������Ă��͂�����������B
�@�i�����͎O�V�����������A���C�̒�����ɂ��Ă��܂����B���̒��H���Ăǂ����Ă���Ȃɂ��������̂��낤�B�j
���@��@��
�@�H��A�ĂјI�V�ɂ���B
�@�������痈���Ƃ����S�O�O��̐^�����ɓ��Ă������j�����A���C�̉��ɍ��|���ė��������ł���B�Ȃɂ��̍H���W�̎d�����낤���A���N���̎����ɓ�������ʂ��Ă���Ƃ����B�u����ȂЂȂт�����͓����ߍx�ɂȂ��B�ł���Ȃ���������߂��ɂ���Ƃ����B�����̒��ł���������Ԃł���B�v�ƍ�����^�̌��t�������B
�@��N�Ⴊ�������̋G�߂ɂ͂܂������̓I�[�v�����Ă��Ȃ����߁A��ʋq�͓���Ȃ��Ƃ����B���N�͒g�~�ŊJ�������܂����B���������u�k��̔铒�E�Ė�(���Ƃ�)����͍���I�[�v���v�A�Ƃ����j���[�X��Ă����B
�@�������Ȃ���܂����C�͊J��������ŁA�����̓����q�̎p�͌����Ȃ������B
�@���Ɣ��d�̂��ߖ�͗��d����B�����ɃR���Z���g�͂Ȃ��B�@���̂��ߘL���Ńf�W�J���E�o�b�e���[�̏[�d������B�@�g�C���͋����ł��邪�A����Ȃ̂��������B
�@�邪�������߁A�������ނ�����ɂ��邩�A�ق��ɑI�����͂Ȃ��B���݂����Ă��܂����A����������Ȃ��̂��s�v�c���B
��������
Copyright c2003-6 Skipio all rights reserved