はんなり京都
食と文化と・・・(2)
2013年3月

(6) 割烹と懐石
祇園や木屋町をそぞろに歩いていると、しばしば“割烹”ということばに出合う。
いっぽうでたとえば“京懐石”など、“懐石料理”ということばも見かける。二つのことばはどう違うのか、素人にはわかりにくい。

夜の祇園白川北通
“割烹”はもともと中国から伝来したことばで、“割”は“切り刻む”の意味、“烹”は煮炊きによって調味するという意味で、まるまる“料理”をあらわす言葉と解してよいだろう。
“懐石”はその、あまたある料理のなかのひとつの方法。
禅の修行僧が空腹を癒すために懐に温めた石を忍ばせたという話を、かつてどこかで書いた。ことば自体はそんなところから導かれているのだろう、茶の湯の世界でポピュラーになった。それを“茶懐石”という。
亭主が客を招待して一汁三菜でもてなす。
一期一会の料理ともよくいわれる。精神性を重んじる日本独特の文化と解するべきで、淡さのなかに人の生きる道や“もののあわれを”求めた。
一汁三菜のあと、小さな昆布を箸でつまみ、沸騰しかけている湯の中に沈め、引きあげて塩でいただく。淡さのなかの“妙味”といえようか、京都には四季折々にそんな文化が常に寄り添っている。
もっとも最近はそんな精神性はどこかに吹き飛んで、「美味しくさえあればいいんじゃないの!」という風になりつつある、そのように感じる。
***
割烹についてもう少し深入りしてみたい。
日本は水の豊かな国で、海や川から揚がる魚種が豊富である。したがって歴史的に“割く”料理を上位にしてきた。生食を第一にしたということ。
“板前”ということばがある。現在では日本料理に携わる調理人のことを総じて“板前”と呼んでいるが、本来の板前は一料亭に一人。大きなまな板の前に座って献立を作り、調理場全体を監督し、仕入れの素材を吟味し、刺身だけを自身の包丁で切り裂くのが役目である。
いまのことばでは“ハナ板”というのだろう。
一流料亭の“花板”といえば立派な技術者で引く手あまただが、あくまで刺身(お造り)が本義なのである。

もっとも京都は内陸の町で生ものを簡単に調達できないから、“烹”の煮炊きの技術が進化した。“おばんざい”などはその典型で、時間をかけてコトコトと煮炊きする。素材のよさとあいまって美味しい煮物ができあがる!
さて今宵の食事はいずこでいたそうか。
(7) 西木屋町“喜幸”
“煮炊き”のことで書き忘れたことがある。
古い言い伝えで「日本料理は生で食べ、焼いて食べ、捨てるなら煮て食え」と。
これが日本人の魚類を食する基本で、“割烹”のことばを借りれば、割主烹従なのである。野菜も同じ考え方で、大根は刺身のケンとして、また下ろし大根として食べるのが初手なのである。
もちろんそんな理屈は古い価値観によるもので、それがすべてだなどとは思いもよらず、煮ることによってもっと美味しい料理に生まれ変わる食材は山ほどある。
そんな祇園の夜を迎えている。
***
目の前で祇園“やすかわ”の板前さんは、大根の皮をむいている。
おでんの具である。
わたしはできるだけ薄くむくのだが、かれは皮を厚く取っている。なぜ?
「おでんにしたときに“えぐみ”が残りますから」という。
時間は午後10時を過ぎている。この夜の二軒目である。
それ以前、西木屋町の“喜幸”で友人と待合わせをして美味しいお酒をいただいている。

あまごがあたかも泳いでいるようだ!
その“喜幸”にて。
どなたがお連れしたのか知る由もないが、今は亡き、食通で知られる開高健さんの額が架かっている。
その文章が奇抜でイイ!
「この店では いい雲古の出るものを
食べさせてくれます。 保証します。 開高健」
わたしが想像するに、開高さんはここで鮮度のよい川魚の唐揚げを食したのでしょう。川魚は季節によってアユ、ハエ、アマゴなどと違うけれども、いずれにしてもご主人が近くの鴨川か高瀬川で網を打って捕ってきたものでしょう。
わたしたちも、水槽で泳いでいるモロコを揚げてもらった。モロコは京都においては高級魚、頭からかじって食す。内臓の苦味が日本酒の熱燗によく合う。
(開高さんの文章はここからきている)、わたしの直感である。

馬刺し

特製のマイク
だそうです!
京都は豆腐が秀逸である。
地下に大きな水がめがあって、古くから豆腐に欠かせない良水がいたるところに湧いた。京都の人は豆腐作りに精を出して今でも有名店がしのぎを削っている。
“喜幸”さんの豆腐は自家製だ、というより豆腐を商っているという。そちらが本業ということだろうか。
この日は青い豆で風味を加えた“かわり豆腐”をいただいた。これは冷やした酒に合う。
店のお父さんがちょいと顔を出して、常連の友人にご挨拶。この方がもう少し若いときにお邪魔できていたら・・・・・とすこし心が残った。
(8) 祇園“やすかわ”
祇園四条通の北側、白川南通とのあいだの一画(末吉町・清本町・富永町)は日本でも有数の歓楽街だ。さまざまな飲食店が味覚と技を競い、バーやクラブが軒を接してならんでいる。
(一方その南側の『祇園』は高級料亭や置屋、お茶屋さんのテリトリーで、しっとりと落ち着いている。)
どの店でも、とんでもなく活況を呈するのはまず、きれいドコロのご出勤前。彼女たちは軽くお腹を満たしたうえで、「いざ出陣!」 となる。 女将の「行ってらっしゃい!」 の一言でファイティングスピリッツに火が点く。また、“同伴”などという古典的なシステムも残っているのでしょう・・・そんなお二人は、もうこの時点から熱気を孕んだ雰囲気だ・・・。
そして、店がはねてからの帰り道、客にご馳走をねだってもう一度立ち寄るというわけ。

“やすかわ”さんもそんな店の一つ。この店は“はんなり”というより“ほっこり”が似合っている。
看板に「菜処」とある。メインはおでんだが、京都の惣菜をお安くいただける。
前述のように、繁盛店は夕刻6時、7時に入ってはいけない。むちゃくちゃ混雑しているから店に迷惑がかかる!だいたい予約が取れない!
この日のわたしたちは2軒目で、時計はすでに9時を回っていた。
「この時間ならゆっくりできる」と具留満氏。
10席ほどあるカウンターと小上がりが2つ、その奥に座敷があって、10人ほどが座れるだろうか。
これを仕切るのが熟達の女将、もとは置屋さんだったというから、その筋の情報に詳しく界隈で知らない人がいないほどの有名人。この方に礼を尽くして案内を請えば、大概のことは可能となる!
というより、祇園は特殊な地域で、そこで生息する人種はたがいに情報を交換しながら助け合い、自分たちの利益を守り通してきた。これは京都という町の歴史が作り上げた特殊性だろう。中世では貴人たちが、その後は武士たちが乱暴狼藉をはたらき、商売人の培った権益を侵害してきた。
だから町の人たちは自然に自衛の本能を身につけた。
情報を共有して利益を確保する。
よいお客さんがいれば、それを大事に育てる。結果的に町の繁栄につながる。
***
3時間以上の長居をしたのだが、何を食して何を話したのか、サッパリ覚えていない。
それだけ快適にお酒をいただいたのだろう。
メニューには各種のバター焼や煮物、豆腐料理、卵料理などなどが載っていた。なかで、今の時期の“お造り・かつお”を頼んだ。
それとおでんネタの豆腐が美味しくて、「なんで豆腐がこんなに美味しいの?」と質問しながらお代わりまでしたことを覚えている。薄口の上品な味が、わたしに合っていたのでしょう。

定番のおでん
もっといろいろ食べた気がします
大根も、これは聖護院大根なのだが、練馬とはどこか違うような気がして・・・。
もうひとつこれを忘れてはならない。ほどよく甘酢のきいた、自家製のしめ鯖だ。酒のあとの食事として味噌汁といっしょにいただいたのだが、これこそが京都の庶民の食いものだ!

〆の押し寿司”さば寿司”
“やすかわ”の女将のブログを訪ねたら、彼女がいかに世話好きで、若い舞子さんや芸妓さんたちに愛情を注いでいるかがよく理解できる。
このブログを拝見するだけで、祇園で一席設けた気分に浸れる。
金5万円也を散財してホンモノを経験してみたいと思うなら、女将に頼めばよろしい。きっとなんとかしてくれるでしょう!
この日も12時少し前、舞妓さんを連れた白髪の老人がそっと入ってきた。キリットしたいでたちで、どんなご商売なのか、想像するのも難しいのだが、この町にはこういう方の着物姿が馴染んでいる。
“やすかわ”のホームページ:http://www.oden-yasukawa.com/
そのブログ:http://www.oden-yasukawa.com/blog/
(9) プチレストラン“ないとう”
翌朝はベッドで普段ではありえない睡眠をむさぼり、10時過ぎに起床。
(さて何処に行こうか?)
急ぐ旅ではなし・・・・・嵯峨野もいいし大原もいいが、若者のデートコースっぽい。
大人はなんとなく、「ぶらり、“楽焼美術館”辺りを歩いてみましょうか」 ということに決めると、『千利休の故居を訪ねて』、という味のある企画ができあがった!
さて腹がすいた。昨夜あれだけ詰め込んだはずなのに、寝ているあいだにすっかり消化してしまい、われながら強靭な胃袋に敬意を表する。
朝昼兼用、“楽”に行くなら御所の近辺・・・「そうだいい店がある、あそこに行こう。洋食がいいでしょう」 と具留満氏が言い放った。

この暖簾をくぐって
さらに奥へ
夜は和の食事、都の割烹にしか目が向いていない。ならば昼は洋食がいい、当然の選択だ。
京都の洋食は、実は評判が高い。これは食の達人たちが認める周知の事実。われ思うに、「京都の人たちも毎回おばんざいだけの食事では我慢できないだろう。いまや世界の料理が日本でしのぎを削っている時代なのだから、『わちきもたまにはステーキを食したい』と望むのは当然のこと」。
かくして京都で洋食の名店が数多く花開いた。
その一つが御所の南側、丸田町柳馬場をくだったところにある“ないとう”であり、プチレストランという冠がつく。さっそく電話を入れるとうまい具合に予約がとれた。
***
御所のなかを時間つぶしにぶらついたあと、京都地方裁判所の西側の街路を下って、その“ないとう”さんに向かう。
「この町はちょっとした民家でもアイデア次第で立派なレストランに生まれ変わる。美味しいものを丁寧に作って、京都風のおもてなしをすればすぐにメディアが取り上げてくれる。観光客は拡大再生産されているから、これほど恵まれたシチュエーションはない!」
両側に板塀の、狭い路地の先にしゃれた暖簾が見えた。
ひらがなの“ないとう”がデザインされていてセンスを感じる。内装も照明もメニューも大人の好奇心を満足させてくれる。それにサービスをしてくれるレディのみなさんも無駄口がなくスマートだ。家族経営かなとも感じたが、よくしつけられている。
***
 ランチメニューが大きく書かれていた。
ランチメニューが大きく書かれていた。
スペシャルAは「ヒレ豚カツ、和牛ハンバーグ、車海老クリームコロッケ」。
スペシャルBは「ヒレ豚カツ、和牛ハンバーグ、海鮮フライ(海老とホタテ)」で、いずれも2500円なり。
うーん?と迷うところだが「B」を選んで、ついでに昼間の生ビール!
オードブルに、メニュー「A」にあるプチ・クリームコロッケを添えてくれるなどは芸が細かい。無言で客の満足感を高める演出はみごと。
野菜サラダも新鮮な香草をシャキっといただいて、いよいよメインディッシュだ。

サラダを美味しく感じるようになった

美しく美味
養老豚のカツは柔らかくて歯に抵抗感がない。海老とホタテのフライのほかに、かぼちゃ、レンコン、ふきのとうの素揚げまでついている。
これじゃあ、ワインに手を出したくなる。が、ぐっと我慢!夜にさしつかえる!
ご飯と味噌汁をいただいたあと、コーヒーとデザートまで。
でも、それぞれが“プチ”だからお腹の負担にもならず、かなりの満足を得ることができた。
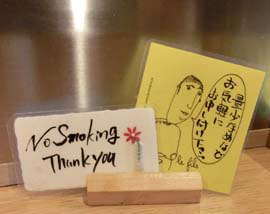
レストランは劇場空間だ。演出家は一家の主のシェフ。食材から洋食器、カウンターのテーブルの板も、もちろん壁にかかる絵画やBGMも、かれはプロデューサーとして素晴らしい才能を発揮してくれた。洋食屋としては最上位にランクされるべき店かと思う。
(ないとうさんのホームページはこちら)
(10) 一条戻り橋&清明神社
「楽さん家の辺りをぶらつくならついでに、“清明神社”にもちょっと寄ってみましょうか!」
昼食を終えてバスに乗って、一条戻り橋・清明神社前で降りた。
ここから東に向かえば利休や楽家の閑静なたたずまいが見られ、逆方向の西北を眺めれば少し離れたところに、かの安部清明(921〜1005)を祀った“清明神社”を認めることができる。

現代・一条戻り橋の華やかさ
“一条戻り橋”は京都市上京区堀川通りにあって、数々の逸話に彩られている。
その昔は平安京の西北端のポジションにあって、都の内と外とをつないでいた。内と外、つまり此岸(この世)と彼岸(あの世)との間に架けられた橋で、葬送の列は、必ずこの橋を渡って遺体を外に葬ったという。
橋の名前の由来について『撰集抄』巻七は次のように記述している。
「熊野の僧・浄蔵が父・三善清行(847〜919)の葬列にこの橋で出会い、しばし観法を行ったところ、父清行が蘇生した」 と。
それゆえ戻り橋という名前がついたようだが、よくある目の錯覚というやつかもしれないし、まさか死んだ父親がそのまま生き返ったということではないだろう。
***
立て看板にはこういうことも書いてあった。
「源頼光(948〜1021)の四天王の一人渡辺綱(わたなべのつな)がこの橋で美しい女性に会い、『夜更けが怖いから送ってほしい』と頼まれたので馬に乗せたら、女はたちまち鬼と化した」とか。
「渡辺綱が切り落とした腕が残り処置にこまったので、すでに有名人になっていた安部晴明さんに相談した」とか。
幼時、爺さんの寝物語で聞かされて記憶に残っている英雄どもが、ここでは次々と現れる。源頼光とその四天王といえば大江山の酒呑童子を退治した武士。深入りすると、闇の世界に連れて行かれそうなのでこのへんで止めておく・・・。
***
 “清明神社”は“闇の支配”どころか明るくて、若者たちであふれていた。
“清明神社”は“闇の支配”どころか明るくて、若者たちであふれていた。
陰陽道(おんみょうどう)とか占い師、“安部清明”といっても、科学全盛の現代ではほとんど「それがどうしましたか?」の世界かと思う。
わたしも夢枕獏さんの小説『陰陽師(おんみょうじ)』がいっときベストセラーになったとき、興味も関心も持たず、その話題を避けてきた。
ただ中世以来これだけの話題を作ったわけだから、なにがしか科学的証明のできることがあるのかもしれない。
そんなわけで、少しつっこんでみた・・・。
当時の平安京には“闇”がはびこって、まさしく真性の、“百鬼夜行”の時代であった。
清明は「鬼を征伐できるのは閻魔大王ではなく、泰山府君(たいざんふくん)であり、その泰山府君に祈祷をすれば鬼に対抗できる」 と唱え、さらに「陰陽師だけが泰山府君と対話ができる」 として、人の心をとらえた。
「闇の時代に活路を開くためには強力な闇の力が必要だ。私は鬼(呪いや邪気)を退治する祈祷を行って民衆を助ける」 というかれの論理には説得力があり、鬼を操れる人物として名声を高めてゆく。
清明は、当時の主流であった真言・天台の密教に対抗して、中華の原始的宗教である道教の概念を昇華して、それを利用する。
「木・火・土・金・水の五つの要素から万物は成り立っている」 「そして万物は男と女、太陽と月、光と闇など、すべてが対になって存在し互いが影響しあって存在している。なかで重要なのは『人と対になっているのは“星”』であり、天体の異常に注視すべき!」という“陰陽五行説”を駆使した。

古来陰陽道で桃は魔よけ、厄除けの果物だそうな!
この桃を撫でることで災厄は逃げてゆく!

この印こそ陰陽師の象徴!
木・火・土・金・水の五つの惑星を結んで何を祈祷するのか?
かれは頭のいい人だったのでしょう。そしてカリスマ性まで持ち合わせていた。
天皇や皇族、殿上人まで取り込んで著しい注目を浴びる。
当時の氏の長者である藤原道長も重用(ちょうよう)したという。
***
陰陽師の得意とした“陰陽五行説”の行為が、現代科学でどういう分析が行われているのかを知らないが、わたしは“勝つ”のお守りを土産に買った・・・。
(11) 利休批判
御所の西側で、堀川通りとのあいだの小路に“樂美術館”はあった。
樂家と初代・樂長次郎を語るには千利休に触れないわけにはいかない。
秀吉が聚楽第を創建したとき、瓦職人として異才を発揮していた長次郎に利休が頼み込んだ。「茶碗を焼いてくれないか」 と。
以来、利休の切腹による短い空白の時代はあったが、400年の長きにわたって蜜月の時間を過ごしてきた。

樂美術館内部は撮影禁止
エントランスで一枚だけ!
京都における利休の古跡といって思い浮かぶのは大徳寺。
山門“金楼閣”に利休の木像を置いたのが、秀吉の怒りを買った。それが原因で死を賜ったという話は説得力に欠けるが、秀吉はよほど憎かったのか、その首を前出の“一条戻り橋”にさらした。
当時の京の人はこれをどのようにとらえたのか知る由もないが、興味深い。わたしの理想の利休像というのは、あくまで自我を曲げずに秀吉に抗って死を選んだ、そう思いたい。
利休論には是々非々がある。
商人文化の発達した大阪・堺に育っているだけに、利休の人格のなかに、“利”が住み着いていたという想像を捨てられない。
すなわち売僧(まいす)の行為。
何の変哲もない茶碗や花入れ、杓子などを高額で売りさばいて利益を懐にした。
茶の湯の純粋な精神性とは正反対と思われる、功利的な行為が、なかったということはないだろう。
***
これから語るのは、柳宗悦氏のことばを借りるのだが、利休に関しての辛口の批判である。
「利休というと『茶』では神様のようにいう人が多い。はじめから鵜呑みに無批判的に、ありがたがっている人が多い。茶人はさておき、学者にさえそういう人が多いのはまことに困る。
利休はたいした才気のある人であったと思われる。性格も強くて傲慢なほど自信があった人であろう。それだからこそ諸大名や武将を向こうにまわして、彼らを手玉にとったほどのやり手であった。だからその影響力はなかなかに大きく、今日『茶』の存在が良くも悪しくも彼に負うところがあるのは言うを俟たない。」
同感!
「だがどういう道を通って、利休はその位置を得たか、利休の生涯を見ると彼は転々として当時の権門に仕えた。信長に仕え、次には秀吉に侍り、その他の諸大名、諸武将、さては豪商と歩き回った。権門を利用することを怠らなかった彼の生活に、すでに不順なものがあったといえる。
常に権力とか金力とかの背景を求めた。『わび茶』とはいうが、一種の贅沢で派手な『茶』で、主として富や力にものをいわせた。仏教が説く『貧』の茶とは遠いものであった。」
柳氏のように、無名の職人の手になる日常雑器の美を探求された方には、利休のやり方は到底認められるものではないのかもしれない。さらに批判の矛先は鋭く、突き刺す!
「太閤は一面確かに風流を好んだ人であろうが、どれだけ美しさのわかった人なのか。黄金作りの茶室や茶器を誇ったほどの幼稚さがあった。太閤を禅味に徹した大茶人などとは義理にもいえない。
そんな彼を相手にして、社会的または政治的位置を得たことは利休を得意にしたかもしれないが、同時に彼の『茶』を不順なものにしたことは否めない。」
そして結論は、「もしも権勢にこびず、もっと民間に『貧の茶』、『平常の茶』を建てたら、茶道はずっと違ったものになったと思われてならぬ。」である。
これらの批判は多分当たっているだろう。
がしかし、日本史は上部構造のなかから歴史に残る美術工芸品を生み出し、それを後世が上手に活用しているように思う。利休や彼の周囲の「千家十職」の職人たちが生み出したモノも、現代に生かされているのではなかろうか・・・。
すこし深入りしてしまったので、美術館にはいって樂家歴代の作品をながめてみよう。
(12) 樂美術館
小粒でも洗練された樂美術館は御所の西側で、堀川通りとのあいだの小路にあった。当世樂吉左衛門の住まいの敷地内だろう。
樂家と樂焼のあらましについては、二度ほどドキュメンタリーで拝見している。したがって現当主の吉左衛門さんについては他人のような気がしない。年齢も同じようなものだから頑張っている姿に勇気づけられることもあった。

格子戸の奥に見えるのは、
本阿弥光悦が書いたという
”御ちゃわん屋”の暖簾*
樂焼は轆轤(ろくろ)を使わない。
自身の指とヘラの感覚をたよりにひねり出す。それゆえ、ふっくらした人肌感覚がそのまま残る。
また大量生産の“登り窯”を使わず、独自の窯に“ふいご”で空気を吹きいれることによって、火力を調節しながら焼き上げる。
「よし、今晩焼き始める!」 と決めると、周りから手なれた職人さんたちが集まってきて、一昼夜で数十碗を焼く。
自身の目で炎を見て、耳で火の勢いを聞いて、出来上がりへの想像をめぐらせる。
この製法は一子相伝(父子相伝〜男系)という。 極意を書いたものがあるわけではない。親から子へ子から孫へ、手と体をもって伝えていく。そうやって十五代400年の長きにわたって継承してきた。
けっして科学的ではないところが、現代では逆に大きな魅力につながる。

初代長次郎 黒楽茶碗 銘 面影
二階の展示室にあがった。この日『樂歴代名品展』と名づけて、初代から伝来の茶碗がずらっと並べられていた。赤と黒のぼってりとした樂茶碗・・・。
しかも十五代それぞれの代表作という豪華さで、茶の湯に嗜みのあるかたにはたまらない。
初代長次郎の黒樂・銘“面影”・・・利休はこの黒樂が焼き上がったとき、ほのかな茶を含んだ黒色、ムダのない、そして温かみを感じさせるかたちの美に感動する。
映画の脚本にしてみると次のようになる。
「これです。掌に載せたときにしっくりとくるふくらみ、そして温かさ、これを待っていたんです」 といって利休は長次郎の手を固く握りしめる・・・。
利休はこの黒を好んで使ったが、秀吉は「陰気だ!」といって嫌った。

三代道入の黒楽茶碗 銘 青山

本阿弥光悦作 銘立峯 追銘五月雨
二代常慶(1561〜1635)、三代道入(のんこう)、四代一入、五代宗入、六代左入とつづく、黒樂赤樂のなかに本阿弥光悦(1558〜1637)の赤樂が混じっていた。
光悦のことを書き始めると長くなるからほんのすこし・・・。
俵屋宗達、尾形光琳とならぶ琳派の正統なる創始者、自身が書や漆芸の達人であったが、古典に造詣の深い有能な工芸プロデューサー、アートディレクターでもあった。
宗達の下絵に自身の書を書き込んだ『百人一首』や『古今和歌集』、『鶴下絵三十六歌仙和歌巻』などはあまりにも有名だ。
光悦は家康に気に入られ、江戸移住を強いられたがそれを拒んだ。秀吉ならきっと打ち首だったろう。家康は洛北の“鷹峯(たかがみね)”に土地を与えた。光悦はここにさまざまな職人を集めて「光悦村!」を形成した。
そこで、二代常慶さんに学んだ楽焼を焼いたのでしょう!
たくさんの楽茶碗が残った・・・。
(13) 利休居士遺跡の辺り

表千家“不審庵”の威容
東京における“都の西北”は早稲田、では“御所の西北”には何がある? 『八重の桜』の同志社といいたいところだが・・・ここでは「ブー」。
小川通りの、寺之内通より北側・・・・・。
利休の子少庵を、秀吉が許して土地を与えた、それがこのあたり。
さらに三代目の宗旦が三人の息子にそれぞれ茶室を与え、表、裏、武者小路の三・千家が成立、茶の湯は後世に引き継がれた。
利休の首が晒されたあと、会津に蟄居していた少庵が許されなかったら現代の構図はなかった。それに奔走したのが当時の会津藩主蒲生氏郷であり、家康であり、前田利家であった。
***
樂美術館の余韻を楽しみながら歩き始めた。
見当をつけたあたりで、買い物がえりの女性に武者小路千家への道を尋ねると、「○○子はんのとこなら、そこやけど・・・」と親しそうな答えが返ってきた。
京都っぽいというべきか、下町風情というべきか、武者小路千家といっても生活者であり、買い物にも出るし隣近所との付き合いも普通にやっている、ということなのだろう。
武者小路の“官休庵”はすぐそこにあった。

武者小路千家“官休庵”
そういえばすこしまえに、その後継者・千宗屋氏が北アフリカの“茶”を訪ねる旅の番組を観た。カサブランカのラジ家を訪ねて互いの国の茶を楽しんだり、遊牧民のテントで素朴な茶を味わったりと、かの地での興味深い飲茶の習慣を披露してくれた。
千宗屋氏は次代の茶道を牽引する人材と注目されていると聞いた。まだ40歳前と若く、随所に才能のきらめきを見せてくれるなかで、最後に漏らしたことばが印象に残った。
「生きるということは水を汲んで、薪を拾い、火をおこして湯を沸かし、茶を飲むこと。飯を炊いてこれを食すること。シンプルだがこれが生きるということ。友と、隣人と茶を飲んで生きる喜びを感じることが大事かと思います」。
豊かになりすぎて忘れていた生きることの原点を、あらためて気づかせてくれた。

裏千家“今日庵”
表千家の“不審庵”、裏千家の“今日庵”が表と裏の配置で、閑静な小川通りにひっそりと佇んでいた。
われらは由緒ある茶室に招かれたわけでもなく辺りをぶらついて、塀の中を覗くおのぼりさん!
たまにはそれもいいと思いながらも、少々歩き疲れた。

俵屋吉富の抹茶セット
さあどうしようかと考えあぐねる目の前に和菓子処があった。暖簾に“俵屋吉富”と書かれている。
簡単に想像できるのは、茶の湯とのかかわり。“千三家御用達”ということを考えるところだが、そんなもんじゃない!御所をはじめとして京都五山の南禅寺、相国寺、建仁寺や、金閣・銀閣その他の門跡寺院など錚々たる顧客がリストにならんでいる。
「じゃあ、ちょっと寄ってみようか」 とあいなった。
甘いものにたしなみはないが、抹茶セットはお疲れ気味の心身を癒してくれた。
(「その3」へつづく)
「はんなり京都」(1) (2) (3) (4) へリンク
Copyright ©2003-13 Skipio all rights reserved