36章 然別湖
<大自然が生んだ湖と山>
然別湖(しかりべつこ)との最初の出合いは学生時代のこと。
10日間の北海道ケチケチ旅行の中盤で帯広に着いたのは、9月も半ばを過ぎ山々が色づき始めた季節で、秋のけはいが漂い始めていた。襟裳から黄金道路、広尾を経由して帯広に入った。竹馬の友との二人旅であったが、前日襟裳岬で知り合った関西から来た旅の学生と意気投合し、ここでは三人になっていた。

午後の2時ごろだったであろうか、駅前でレンタカーを借り、北に見える山裾を目指して走った。
秋の山の夕暮れは想像以上に早いので、のんびりと走ることは許されない。わたしたちは両側に果てしない牧場が広がる、十勝平野を疾駆して湖の畔にたどり着いた。
然別湖と糠平湖とは隣り合っているが、糠平湖が人造湖であるのに対し、然別湖は正真正銘の自然湖で、当時すでに秘境の湖の名声を勝ち得ていた。原始のままの、森に囲まれた静かな湖であった。
もう夕暮れがそこまで迫っていたので、人のけはいはまったくなく、シーンとした湖畔にたたずんだ若い旅行者は「これが求めていた北海道!」とわけもなく特別な感慨に浸った。怠惰な都会生活に慣れきっていた三人のハートに訴えるに十分な、北海道らしい寂寥感が漂っていた。短い嘆息の時間はすぐに過ぎ去り、すっかり暗くなって寂しさがつのる湖を後にし、闇の街道を帯広に向かって走った。このとき、再びこの湖との出合いはないものと思ったのだが・・・

はたして幸運にも、札幌転勤によって思いもよらず然別湖との再会を果たす機会を得た。
十勝の清流
1995年秋。
この日は日高から「石勝樹海ロード」を経由し、喜び勇んで森の湖に向かっていた。助手席には、大学に通う子供の母親となったカミサンがいた。ということは、あの記憶の日々からすでに20数年を超える歳月が過ぎていることになる。
 日高と十勝の国境・日勝峠を越えて、「清水町」をクロスすると間もなく十勝川にぶつかる。十勝川は水源を大雪山の南部・十勝山系トムラウシに発し、日高山脈、大雪山系、阿寒山系の水を集めて太平洋に注ぐ。ちょうど十勝平野の真ん中を貫流していることになるが、その清冽な流れは水質がきれいなことでも群を抜き、支流・札内川は日本一の清流として名高い。青い空と流域の草紅葉とを背景に滔々と流れる十勝川・・・気持ちがいい。
日高と十勝の国境・日勝峠を越えて、「清水町」をクロスすると間もなく十勝川にぶつかる。十勝川は水源を大雪山の南部・十勝山系トムラウシに発し、日高山脈、大雪山系、阿寒山系の水を集めて太平洋に注ぐ。ちょうど十勝平野の真ん中を貫流していることになるが、その清冽な流れは水質がきれいなことでも群を抜き、支流・札内川は日本一の清流として名高い。青い空と流域の草紅葉とを背景に滔々と流れる十勝川・・・気持ちがいい。
十勝川を越えると「鹿追町」にはいる。道路標識は「左・然別湖」の案内をして導いてくれる。10数キロ進んだところでさらに道は二つに分かれる。「左・菅野温泉」「右・然別湖」。右手に道をとると、途中「扇が原展望台」から、十勝平野の雄大な全貌が見わたせる。おそらく道内の展望台としてはベスト5に入るのではないだろうか。秀逸である。
扇が原を越えると間もなく然別湖が姿を現した。
紅葉の然別湖
秋は原始の自然ならではの神秘的な紅葉が堪能できる。湖面に映る姿と合わせて唇の形に似ていることから通称唇山と呼ばれている天望山をバックに、赤や黄色に色付く原生林は美しい。水辺の道を散策する。湖周辺の樹木は主に黄葉が多いようだ・・・

しかし湖畔には、立派に整備され温泉ホテルが目立つようになった。こうなると秘境もただの観光地でしかない。なんだか寂しい気持ちは否めないが・・・
真白き然別湖
 1997年冬。
1997年冬。
極寒の2月初め、再度訪れる機会を得た。
湖面はすっかり凍りつき、50cm以上も厚くはった氷上はスノーモービルやクロスカントリースキーなどのウインタースポーツをを可能にし、十勝の若者を招き入れる。
 その湖畔からあまり遠くないところに「IGLOO・VILLAGE・然別コタン」と称する氷の家が建っていた。エントランスから動線を引っ張って、中には氷の彫刻が並び、カクテルやビールが飲めるバーの設備が整えてある。若い人たちの発想だろうが楽しくていい。おまけに氷のグラスで呑むのだからこれはおいしいに決まっている。ただし、氷の家の中だけに冷えること請け合いで、小水の近い方は遠慮しておかないと始末が悪い。
その湖畔からあまり遠くないところに「IGLOO・VILLAGE・然別コタン」と称する氷の家が建っていた。エントランスから動線を引っ張って、中には氷の彫刻が並び、カクテルやビールが飲めるバーの設備が整えてある。若い人たちの発想だろうが楽しくていい。おまけに氷のグラスで呑むのだからこれはおいしいに決まっている。ただし、氷の家の中だけに冷えること請け合いで、小水の近い方は遠慮しておかないと始末が悪い。
インディアンになれなかった男
その然別コタンで「星の物語」と題し、星野道夫さんの遺作写真展が催されていた。
昭和27年(1952)千葉に生まれた星野さんは慶応を卒業後アラスカに移り住んで20年、マイナス40度の氷河地帯で一人でテントを張り、オーロラの写真を撮り、極北の地に生き続ける鯨や北極熊、カリブーなどの生態を追い続けた。1996年8月8日ロシアのカムチャッカ半島クリル湖畔で熊に襲われて死亡。
わたしたちがこの遺作展に出合ったのは彼が亡くなってちょうど半年後のことだった。星野さんのことばを紹介することで、かれの人となりを少しでも理解できるのではなかろうか。
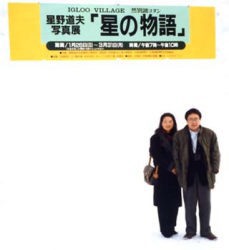
「十代の頃、神田の古本屋で、ある一冊のアラスカの写真集を見つけた。なぜ、こん
な地の果てのようなところに人が暮らさなければならないのか。」
「巨木の闇を抜け、森に足を踏み入れると、あたりは夕暮れのように暗くなった。かすかなクマの道が森の奥へ続いていた。クマに出会いたいのか、それとも出会いたく
ないのか。自分でもよく分らない気持ちを抱きながら、僕はゆっくり進んでいた。」
「アラスカの山を見ていて、熊をぽつんと見たときに、やっぱり見入ってしまうんですよね。熊が生きている不思議さっていうのは最終的には自分自身の持っている不思議さなんで、それを通して自分の生きている事の不思議さを再確認しているっていうか・・・。」
彼の眼差しの中には、 個体の死を越え、種の違いを越えて連綿と続く、大いなる命、悠久の命への畏怖と愛
があった。 「インディアンの教え」の中にも埋め込まれているが、ネイティブの古老達が語り伝える神話の中に秘められた、人間が大地から生命をもらい、大自然の営みと調和して生きてゆくための様々な叡智を、未来の世代にどう伝えてゆくべきかを探す旅をかれは始めていたのに・・・。
作家・池澤夏樹が週刊朝日に寄せた弔辞は星野さんの気持ちを代弁していた。
『アラスカに、カリブーやムースやクマやクジラと一緒に星野道夫がいるということが、ぼくの自然観の支えだった。彼はもういない。僕たちはこの事実に慣れなければならない。残った者にできるのは、彼の写真を見ること、文章を読むこと、彼の考えをもっと深く知ること。彼の人柄を忘れないこと。それだけだ。』
<続く> (2005.5.15記)
Copyright ©2003-5 Skipio all rights reserved