30章 石狩「番屋の湯」と
鮭料理「金大亭」
<石狩川河口・番屋の湯>
<石狩市>
石狩市は1997年に念願の市制をしいた。その石狩川河口に誕生した温泉「番屋の湯」の評判が高い。一度は入湯しておかないと北海道フリークが泣く。ということで春3月、雪もまばらに残る石狩に勇んで出かけた。
札幌南部の自宅から小樽に向かい、小樽カントリーの前を通り過ぎると、石狩は目と鼻の先である。
ここは熊笹が茂る石狩川の河口近くで、漁業の街、田舎の寒村という雰囲気がある。
石狩川は、今さら説明するまでもないが、北海道第一の河川「母なる川」である。北海道の屋根といわれる「父なる山」大雪山系から286キロの長躯を旅して日本海に注ぐ。石狩市はその河口にあたり、未開発の広大な原野が広がり、トラックのターミナルなど倉庫や運輸系の企業が幹線道路脇に目立つ。
途中交通事故を見てしまった。なにを血迷ったか、民家の角に飛び込んだ車が悲鳴をあげていた。ハンドルを切りそこなって止むを得ず突っ込んでしまった様子だが、昼間からひどい場面に遭遇してしまった。
しかし人の振り見て我が振りなおせ。あなたもいつ事故に見舞われるかわからない!
<ベンツも行く>
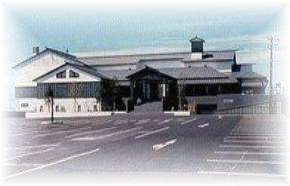 前をベンツの新車が走っている。
前をベンツの新車が走っている。わたしの感で「このベンツも番屋の湯行きだよ。」と漏らす。案の定、番屋の湯の駐車場に入って行った。
それほどに有名で、大規模で新しい、公共の温泉なのである。いつも駐車場は満車である。
湯船も芋の子を洗うようである。
「特に女風呂はすごい。体を洗うのに女性は時間がかかる。洗い場を確保するのがたいへん。」わたしは覗いてみたことがないからわからないが、女房どのの指摘である。
ゆったりとしたくつろぎを目的に行く温泉で、陣取り合戦というのは納得が行かない。人気のありすぎというのも困りものだ。
<化石海水>
「番屋の湯」の湯は塩味がする。海が目の前ということから、「これ海水じゃないの」と思う。そう、実はこの湯は海水なのだ。しかし単純に海の水をそのまま持ってきたわけではない。地下数百メートルから汲み上げられた大昔の海水、言うなれば「化石海水」なのだそうだ。ここの地層は海底に積もった砂や泥が広く分布していて、石狩市ばかりでなく札幌市など石狩低地帯の地下深くまで続いている。
湯は地下にあるこの地層から汲みあげられたもので、地質時代で言う新生代新第三紀の末ごろ(1千万年前〜数百万年前)の海水。まさに太古の海水なのです。
しっかりと浸からなくては・・・!!
<日本海に沈む夕陽>
「番屋の湯」で、湯上りのビールを飲みながら日本海に沈もうとする太陽を眺めた。沈みゆく太陽は早い。滑るようにすばやく、あっという間に水平線のかなたに沈んで行った。こういった景色を眺められるのも北海道ならでは、一期一会の大切さを強く感じる。
そう言えば今日は春分の日、太陽は赤道の上にあって昼と夜の長さが同じ。そういった日に太陽の沈むさまをじっくり見ることができたのも、なにかの縁。
そして北海道はこれから春に向かって一目散なのである。
<金大亭>
石狩といえば鮭の本場。というより日本海沿岸のこの地方には、昔から鮭の群来(くき)があった。
したがって鮭料理は本場の味。多くの鮭料理著名店があったのだが、鮭漁の衰退とともに漁業自体が下火になったのか、今は残る店も少ない。
その中で「金大亭」は明治13年創業というかられっきとした老舗の名店。
遅い秋の夕方、コース料理を予約して店に入った。明治の建築というだけに、いや加えて北の潮風に吹かれてきただけに木造の建物は白茶けて痛んでいるが、そのことにむしろ風格を感じた。
突き出しのイクラ醤油漬けに始まって、氷頭(鼻の軟骨)なます、ルイベ(刺身)、メフン(血合い)の塩辛などと鮭料理のオンパレード。焼き物は江戸時代の製法で約8カ月かけてつくる「寒塩引」。
鮭の身に味噌と野菜を混ぜて蒸し焼きするチャンチャン焼きも食卓を飾ったが、この手の料理はお酒のお供に絶好で、銚子の数が並んだ。
<石狩鍋>
さてメインはこの店が発祥という石狩鍋。味の要になる味噌は、甘めにつくった特製味噌を使用。切り身はもちろん、頭やアラまで余すことなく材料として利用するのでいい出汁が出る。鮭も本望というところか。
豆腐、糸こんにゃく、春菊、玉ネギなど他の野菜や具材もたっぷり入れるが、白菜ではなく、キャベツを入れて甘味を出している点が、おいしさの秘訣なのだそうだ。そして、最後にさっとふりかける山椒の香りが味噌の臭みをとり、おいしさを引き立てる。
この店の苦労と歴史のひとコマを覗いてみたくなった。
<大黒屋の創業> 明治十三年、最初は「大黒屋」の屋号で創業した。 初代石黒サカは新潟県からの移住で、当時はサケ漁が盛んで、町も繁栄していた。彼女はそこで、漁師を相手に商売をしようと思い立ち、割烹料理の店を開いた。 以来、この店は代々、女性が継承してきた。二代目コウも三代目トクエも壮健で、とくに二代目は八十歳を過ぎた高齢でも、最期までお座敷回りをしていたほどの元気さ。このかたは研究熱心で、サケの頭から尾の先までを材料にして「氷頭なます」や「焼き白子」など新たな料理法を考案した。そのおかげか現在のフルコース料理の品数は15品。 当時の石狩はサケの千石場所で、漁師たちはずいぶん豪勢な遊びをしていた。この店も芸者を何人も抱えており、その名残りの道具類がいまも店に飾ってある。町内には遊廓なども何軒かあったようで、漁労に精を出したあとの遊びはどの町でも同じ、豪放磊落に大胆な遊びに熱中したようである。 (そんな話を道内の港町のあちこちで耳にした。) |
近年、石狩の鮭は道内でももっともおいしいという。その理由は、人工孵化した卵の放流を上流の千歳川ですることにある。帰ってきた鮭は脂をたっぷり身に蓄えて千歳に里帰りしようとする。その途上、入口の石狩河口で捕まえてしまうのだ。
人間にたとえれば、奉公に出た娘が盆ぎりで里帰りするが、家を目前にしてさらわれてしまうというような残酷な話。鮭もつらい。
かくして涙をこらえながら、わたしはおいしい石狩鍋をいただいたのである。
<番外・日本で最初の鮭の人工孵化> 明治10年、魚の缶詰を作る技術指導のため北海道にやってきたU.S.トリートというアメリカ人が「鮭は人工孵化が可能で、アメリカでは実用化された技術だ。」と教えた。 それを聞いて感心を持った男がいた。 明治13年に札幌農学校を第1回卒業生として巣立った伊藤一隆がその男。北海道庁の水産課長に就任した伊藤はすぐに渡米、メイン州バックスボードの孵化場で人工孵化技術を実地に学習し戻った。そして明治21年千歳川上流の湧水の地・烏柵舞(ウサクマイ)という山中に、日本で最初の鮭鱒の人工孵化場を立ち上げた。 |
<続く>
![]() (幌加温泉へ)
(幌加温泉へ)![]() (朝日温泉へ)
(朝日温泉へ)
北海道トップへ | ホームページトップへ
Copyright ©2003-6 T.Okamoto all rights reserved