フグを訪ねて九州へ (その4)
博多・阿蘇・熊本 2012年2月
(8) 阿蘇五岳を独り占め
春の日和に恵まれて、霞のかかった九州自動車道を益城インターで降りて阿蘇に向かった。
熊本空港の手前を右に折れ、田植えを待つ田野の中を左に阿蘇の端を目に入れて、右の山手へと上り詰める。
「とにかく阿蘇が目の前に広がって、その景観が雄大で、ぜひみなさんに一度観てほしい!」
ホスト役のTさんのことばに期待が高まる。

左、噴煙か

開墾が進む
車の中で阿蘇の命名とその意味について考えてみた。
“阿”は「山や川の曲がって入りくんだ所」という意、そして“蘇”は「生きかえる」、「よみがえる」の意、これを合成すると、「常に噴火していたために地形が複雑に入り組み、それでも繰り返し甦ってきた山脈」 というようなことだろうか。
いまだに活発な噴煙を上げる活火山で、この日わたしは“野焼き”でもやっているのかと勘違いしたが、二箇所で噴煙が上がっているのを見た。
「阿蘇山」の名は通称で、正式には「阿蘇五岳(あそごがく)」という。
間もなく、外輪の中腹に堂々と立つホテル「グリーンピア南阿蘇」に到着。
ロビーの一枚張りの大窓から、横に広くドーンと居座る五岳を眺め観た。
「Oh beautiful! この借景はいい!」
部屋の窓も、額縁のなかに阿蘇がすっぽりとおさまるような設計がなされていた。

雄大な景観 阿蘇五岳
阿蘇が夕陽に染まっている。
五岳とは具体的に、高岳(1,592.3m)を最高峰に、中岳(1,506m)、根子岳(1,433m)、烏帽子岳(1,337.2m)、杵島岳(1,321m)といった1,300m以上の山々を言うが、それらが横に山脈を形成し、あたかも寝そべる牛のようでもある。
いま噴煙が見えるのは中岳だろうか?
 「さあ、早く、早く!」 「夕陽が沈む前に風呂に入らねば」と、露天の温泉に急いだ。
「さあ、早く、早く!」 「夕陽が沈む前に風呂に入らねば」と、露天の温泉に急いだ。
ここから1時間、西日を浴びた山々に、少しずつ影ができて、それは徐々に東から西へと移動し、やがて宵闇がせまるさまを、倦むことなく眺めていた。
そうするとカルデラの中に点在する家々に、ポツリ、ポツリと明かりが灯り、生活の営みを気づかせてくれる。
日はトップリと暮れ、阿蘇の山々も黒々としたシルエットに変貌した。
そろそろ夕食の時間だ・・・。

夕食は館内のレストランで洋風コース料理をいただいた。
前菜、自家牧場産馬肉のタタキ、マグロのカルバッチョ、南瓜のスープ、鯛・ズワイ・チーズの包み焼。ここで口直しのゼリーが入って、〆は黒毛和牛の溶岩焼き!

マグロのカルバッチョ

たたき
そしてさらに、おまけのバイキングから“ザルそば”とデザートの“ヨーグルト+アイスクリーム+果物+コーヒー”までいただいてしまった。
際限のない食欲に、自分自身もビックリはしたが、一日の疲れと心地よい酔いで、幸せという海のなかを泳いでいる気分であった。
(9) 阿蘇と文学

雲に隠れて五岳が顔を見せない
どんよりした空から
ぽつりぽつりと冷たいものが
阿蘇は「火の国」熊本のシンボル的な存在として親しまれている。火山活動が平穏な時期には火口に近づいて見学できるが、活動が活発化したり、有毒ガスが発生した場合は火口付近の立入りが規制される。
阿蘇ときいてすぐに頭に浮かぶのは、三好達治の詩『大阿蘇』における“草千里”の情景である。
“草千里”のことばを覚えているのは、国語の教科書に載っていたからだろう。
雨の中に 馬がたつてゐる
一頭二頭仔馬をまじへた馬の群れが 雨の中にたつてゐる
雨は蕭蕭と降つてゐる
馬は草を食べてゐる
尻尾も背中も鬣も ぐつしよりと濡れそぼつて
彼らは草を食べてゐる
草を食べてゐる
粛々と降る雨は春の雨だろう。
宿泊した翌日のわたしたちにも雨は襲いかかった。しかしこちらは冬の雨でいささか冷たい。せめてあと半日もって欲しかったが・・・。
そして次の話題も阿蘇の雨、といってもこちらは台風だ。

1953年中岳の噴火
明治の半ば、漱石は熊本で数年間を五高教授として過ごしているが、その記憶をもとに二つの作品を残している。ひとつは名作『草枕』で、もうひとつはあまり知られていない短編で、『二百十日』という。タイトルが示すとおり、台風の日に阿蘇に登るという話である。
前日温泉で楽しく過ごした主人公の二人(漱石とその友人)は、いよいよ阿蘇に登ろうとする。
ところが台風がやってきて、たいへん難儀する。
漱石がそのとき読んだ俳句が残っている。
<阿蘇の山中にて道を失ひ終日あらぬ方へさまよふ 二句
灰に濡れて 立つや薄と 萩の中
行けど萩 行けど薄の 原廣し >
台風と噴煙に襲われてあたふたしている様子が目に見えるようである。滑稽のようにも思う。
この実話は文学作品の『二百十日』では次のような表現になる。
<濛々と天地を鎖す秋雨を突き抜いて、百里の底から沸き騰る濃いものが渦を捲き、渦を捲いて幾百トンの量とも知れず立ち上がる。その幾百トンの煙りの一分子がことごとく振動して爆発するかと思はるるほどの音が、遠い遠い奥の方から、濃いものと共に頭の上へ躍り上がってくる。
圭さんが、非常に落付いた調子で、 「雄大だろう、君」と云った。
腰から下はどぶ鼠の様に染まって、殆ど下水へ落ち込んだと同様の始末である。>
やはり偉大な文学者は目のつけ所が違う。
阿蘇は台風が来たり大爆発を起こしたりと、常ではない事件が起きないと作品にならないのである・・・。
「イヤ、そんなことはありませんよ。私は二人の主人公を通じて、時代の青年たちに人の生き方について書いているだけですから」。
漱石先生はきっとそういうでしょうね。
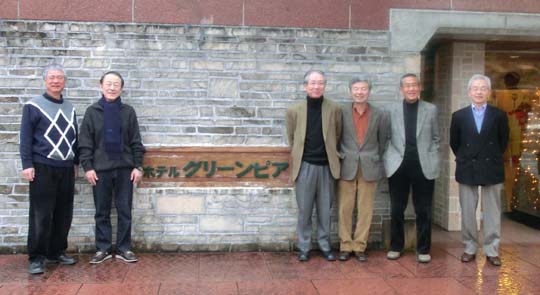
旅の仲間たちが姿を現した!
Copyright ©2003-12 Skipio all rights reserved