京都の秋
(1)奇祭鞍馬の火祭り
2013年10月

時代祭り 皇女和宮
(1)時代祭り
昔の人は優雅な会話を交わした・・・落語「青葉」の噺!
隠居さんが植木屋に昼の酒をふるまっている。
酒の肴に青葉をご馳走しようと、奥方に声をかける。奥方が出てきて、「鞍馬から牛若丸が出まして・・・」と謎のような返事をする。
「牛若丸・・・九郎判官・・・九郎・・・食ろう」の仕掛け。つまり「青菜は食べてしまってありません」というご返事をされたというわけ。
「では、義経にしておけ」 がご隠居の謎ことば。
義経の「よし」を「止し」にかけ、「食べてしまったのなら仕方ないな」の意。当意即妙、スマートな受け答えに感心してしまう。
***
その鞍馬にやってきた。
長年の望みがやっとかなった。
祇園の老舗料亭・鳥居本の女将がいみじくも漏らしてくれた。「時代祭りはオナゴさんのお祭り、鞍馬はオトコさんのお祭りですやろな!」
言わずもがなの“火祭り”詣で、勇壮な男の祭、一度は見ておきたかった・・・。
この日京都に到着するとホテルに荷物を預けてすぐに時代祭り見物に出た。
鞍馬の話に踏み込む前にすこし前置きを語っておきたい・・・・・
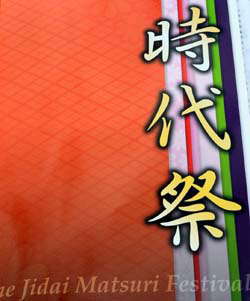
京都は祭りの町、有名な祭りが三つある・・・。
その三大祭といえば上賀茂神社と下賀茂神社の葵祭、八坂神社の祇園祭、そしてこの日の時代祭。
時代祭は平安神宮の祭礼だが、始まりは他の二つと比べてきわめて新しい。そもそも平安神宮は明治28年、平安遷都1100年を記念して、桓武天皇を祀るために造営された。そのとき記念の奉賀行事として、各時代の衣装で行列したのが始まりだ。
ただ、1回目は単なるパレードだったのが2回目からはかしこまって、「桓武天皇の神霊を奉ずる神輿が市中を神幸する行事」となってしまった。
つまり神性をはりつけたということ。そこに安直な精神があったのかもしれない。
だから京都人は時代祭りをママコ扱いする。
「葵やら祇園やらは古いもんどっせ、しやけど時代祭は・・・・・なぁ」 と。
さもありなん。
何も知らない東京っ子はありがたがって、いそいそと集まって眺めているけど、「そんなもん、京都人にはどうということあらしまへん」なのだろう。
なにしろ京都には普段から山ほどの祭があって、そのお祭りを追っかけながら生活をしているという風潮があるのだから。
わたしたちは市民やアルバイト学生の仮装の行列を、烏丸御池の辻から北に歩きながら鑑賞した。
西郷隆盛や坂本竜馬、中岡慎太郎、高杉晋作、吉田松陰らが目の前を通り過ぎる。歩く動作がどこかぎこちないのは、心のうちに恥ずかしさがあるのだろう。イヤ、今の若者は羞恥心などということばをしらないはずだけど・・・。
孝明天皇の異母妹で徳川十四代家茂に嫁入りした和宮も通りかかった・・・。
「あれ、人形だろうか?」
そんなわけはない!なんといっても皇女、あくまでもおしとやかに・・・瞬きすらも許されない?

三条実美だろうか?

愛嬌を振りまく
市長と議会議長
「このまま観ていたら1時間以上かかるから、そろそろ食事に出かけましょう!」
この日のメーンイベントはあくまで“鞍馬”である。すべてのタイムスケジュールはそれに合わせてある。
さらっと見回したあと昼食の『グリルフレンチ』へ。烏丸御池から押小路通りを二条城に向かって5分ほど歩いたわかりにくいところにそのレストランはあった。
京都でなんでフレンチなのかという疑問はおありでしょうが、このあと京料理の予定がズズイと連なっていましたので、それを交わす意味での評判の洋食レストランというわけ。
どんな美味しいものでもつづけていただいたら飽きまっせ!
(2)鞍馬へ
山に入り込んだのは早い時間だった。
一般車“入山禁止”のところを営業車(タクシー)は登っていける。「ここまで!」という停止線で下車して、あとはせせらぎの音を聞きながらゆっくりと歩く。つかず離れずのところを叡山電鉄が走り、わたしたちを追い抜いてゆく。時刻はまだ午後の4時、電車も空いている。
ぽつりと民家が見えてきた。つづいて次の家・・・それらの家々の軒先に大小の松明が重々しく鎮座している。火祭りの予兆がここにあって心のうちは穏やかでない。

こんな大きな松明を担ぐ?
下のは子供用

天狗が睨みを利かせる
(どの家でも火のついた松明を背負うのだろうか?)
「担ぐことのできる男衆のいる家では、みな松明を出します」。
軒先にいたご婦人が答えてくれた。
大小さまざまだが、こんなに大きなものでも担いでしまうのかと、驚くほどのものもある。
昔は力持ちが多かったのだろう、一人で担いだようだが、いまどきの軟弱な勤め人にそんなことができようはずもない。2人で持ち上げるのが精一杯、見るからに重そうだ。
家々の襖を開いて先祖伝来のお宝が並べられている。荒々しい綱の後に金屏風を飾る。山奥の村なのに、京都の優雅さを感じさせる。屏風、甲冑、生け花、小さな松明、矛などバラエティに富んでいて、村のいたるところに『誇り』がある。
1年に一度のお披露目なのだろう。なかにふる寂びた天狗の面が目に入った。鞍馬らしい。
天狗神話は日本の霊山に多い・・・天狗は深山に住むという妖怪で、山伏姿、赤い顔に高い鼻、背に翼がある。手には羽団扇(はうちわ)・太刀・金剛杖等を持つ。神通力があって、自由に飛翔する。
バサバサバサっという音を立てて飛べばどんな人間でもブルッと震える。
鞍馬で修行した義経も天狗になった・・・。
***
鞍馬の火祭は毎年10月22日に行われる。鞍馬山中腹の由岐大明神(ゆきだいみょうじん)を舞台とする祭で、太秦の「牛祭」、今宮神社の「やすらい祭」とともに「京都の三大奇祭」とされている。
山門付近まで一回りしてみたが、さてどこでどう観ていいのやら要領がつかめない。

山門近くに置かれた二基の神輿
「今はまだ観光客も少ないけど、この先押し合いへし合いになるようだから食事をさきに済ませましょう!」
途中、下鴨で評判の『花折』で鯖寿しを調達してきた。
いわずもがな江戸時代、若狭から都まで新鮮な鯖を塩漬けして運んだ。都でこれを調理したのが“鯖寿し”、『花折』はその鯖街道の花折峠にあったことから店の名になった。
私たちは川のほとりの狭い場所で小宴を開いた。一人三切れずつの分け前は、ほとんど立ち食い状態。忙しないけれども、ちょうど小腹の空いたときだったので美味しくいただけた。
このあと“鯖寿し”には何度も世話になり、土産にも買って帰ることになる。

暗闇がせまってきた
大原から山を越えてきたという登山者
隣で一休みしていた男たちの会話が漏れ聞こえてきた。
「ワシらは伏見から来たんやけど、大原から6時間かけて山を越えてきた!」
たしかに登山者のいでたちである。地図を眺めてみると大原と鞍馬はどちらも京都の北方で、指呼の間にあった。

やっと火が入った
(3)暗闇の火
「今を去る原始の昔の、夜はいつも真っ暗だった・・・・・」
そんなナレーションであったか、暗いところから始まる芝居をサントリホールかどこかで観たことがある。たしか三枝成彰がプロデュースであったような。
そのあと林英哲の大太鼓のひとり打ちで舞台はがらりと変わった・・・昔のはなし。

神秘を演出する炎
闇、わたしの記憶では、50年前すら日本には暗闇がはびこっていた。
光があるのは町のなか、ひとたびそこを離れた瞬間、暗闇のなかに魑魅魍魎が跋扈していた。
本文とかけ離れてしまうけれども、当時は街灯などのほとんどなかった時代、インフラという言葉をつかえば、小学校の教科書に「日本の道路の舗装率は10%未満」と載っていたころのことで、田舎の道は雨が降ればぬかるみの泥道となった。
そんな時代の“明るい夜”は年に一度の、収穫を祝う祭りか盆踊りぐらいで、普段の闇夜が怖かった。
「鞍馬の火祭」はまさしく秋の夜長を明るく過ごすことのできる“特別な祭”、一晩中明るいということは日常の労苦からの解放であり、喜ぶべき非日常だったのだ。
夜を徹してふんどし姿の男たちが、松明を担ぎ神輿を担ぎ、人を担ぐという一点をとらえるだけで、この地に住まう人々の祭に対する情熱のありようが伝わってくる。
真っ暗な夜に松明の燃え盛る炎は幻想的かつ神秘そのもので、あるいはまた特別な感情と特別な行為をなさせるものでもある!
***
炎については様々な記憶がある。五衛門風呂を薪で沸かした時代の炎、林間学校でのキャンプファイアのパチパチと木々が燃える音と怪しい炎・・・それらとは別の忌まわしい記憶もある。
肥料店を営んでいた友人の父親の大店(おおだな)が目の前でメラメラと燃えて崩れ落ちてしまったこと。
炎と火事からの連想で頭に浮かんだのは、まず明暦の大火のこと(1657年の江戸)。女の情念が籠もった逸話があって、“振そで火事”という名が歴史に残った。
京の都もさまざまに焼かれた歴史を残していて、そのもっとも悲惨なできごとは“応仁の乱”だろうか、十数年にわたる戦乱で市中のほとんどを焼き尽くした。
野蛮な時代の、これも日本人の歴史だ。
明治以降では「金閣寺炎上」が大きな話題になり三島由紀夫や水上勉がそれぞれの美学で小説に書いた。
江戸では「火事と喧嘩は江戸の華」といった。たしかに対岸の火事は美しいものだが、自身がこれに見舞われたらこんなに恐ろしいものはない。
その火祭りの松明をこれから見ることになる!
18時すこし前、「神事にまいらっしゃぁれ!」の掛け声による「神事(じんじ)振れ」が目の前を走り抜けた。さあ、今から火祭りが始まる・・・。

「神事にまいらっしゃれー!」
(4)サイレヤ サイリョ
午後6時、まず小さな松明を担いだ子どもたちが動きはじめる。
その掛け声は文字に記せば「祭礼や祭礼!」なのだが、言葉にすると「サイレヤ サイリョ!」の叫びとなる。
その「サイレヤ サイリョ!」があちこちから聞こえてくる。どうやら待ちに待った火祭が始まったようだ。一斉に松明に火がともる。
男たちは祭装束に着替える。黒締込みと下がりは力士のパワーを腰に宿すため、黒脚絆は飛脚の脚力を足に宿すため、災いを避けるため南天の小枝を腰に挿す。
猿田彦命(さるたひこ)のついた矛が動き出す。猿田彦命は天狗に似ているが、天孫降臨の際に天地を照らして助けたという話から、火祭りの先導役となっている。
一番太鼓が打ち鳴らされて松明行列が出発する。
いよいよ出陣だ!
***
このころから見物人が急に増え始めた。叡山鉄道がピストンで満員の見物客を運び込んでくる。一本道の狭い街道は人で埋まり、その整理のために大挙動員された京都府警の警察官たちが道路の両脇に3mおきに並んでいる。
その物々しい警戒振りは、かつて某かの事故があったに違いないことを想像させる。それだけ危険がイッパイなのだ。
歩道を示す白線に沿ってロープが張られ、「線の内側にはいってゆっくりとお進みくださーい」 と叫び始めた。ハンドスピーカーからの絶叫は凄まじく耳に響く。
本来こういった山里の祭は静かに眺めたいもの、という思いがあるのだが、その願望は警備のみなさんのかん高い叫びにあえなく潰(つい)えた。
一方通行を強いられ、その流れのなかで前に進むしかない。

少年たちも気合を入れて!
火松明の動きがあわただしくなってきた。
「サイレヤ サイリョ」 も
小さな松明のなかに少しずつ大きな松明が混じるようになってきた。大松明とは違って中くらいな松明の先端に火のついたやつを中学生が担いでいる・・・。
周回コースの基点は神輿が置かれた山門である。
そこから道路に沿って右まわりにロープの周遊コースが作られ、観光客は歩かされる。観光客は否が応でもそのなかに組み込まれる。そうだ、レーシングカーの“F1”のコースを連想してもらえばわかりやすい。
家々の軒先に置かれた松明に火がついて、パチパチと燃え盛る炎に照らされると顔が熱くなる。担いでいる若者たちはきっと火傷(やけど)状態だろう。それでも男の子は我慢の子!父親も、爺さんも、そのうえの彦爺さんもみんなが同じことをやってきた。泣き言を言う暇はない。

「サイレやサイリョ!」
(4)秘の神事
火祭りは夜中におこなわれる祭りだから神秘性がいや増す。
といえばいまも夜中の秘事のように聞こえてしまうが、そのあたりはどうだろうか?
さまざまなリスクから身を守るため厳重な警戒のもとに、宵の口から始まって日付が変わるくらいにはお開きになる、と想像する。
しかし“神事”である。
神事に現代の法律は馴染まない。
真実は、オマツリ経験した人でないとわからない。そしてそれが真の火祭りなのかもしれない。
***
火は力の源で、その祭典だけに内側を覗いてみたいという欲求が高じてきた。
また山奥でおこなわれることも興味深い。日本では山中の祭礼が多い。そこには古くから地の神様、地の精霊たちあるいは自分たちの祖先が祀られていて、年に一回は現世に呼び戻してお礼を言う。そんな崇拝の儀式が千年以上もおこなわれてきた。
鞍馬においても山から里に神様をお呼びして、きちんとしたもてなしをして山に戻ってもらう。
その全部を確認してみたいのだが・・・。

火の勢いは一気に凄まじく
8時になると大松明に火がつく。
狭い坂道の街道にその大松明が一斉に立つ。
煙が村全体を蔽い、バチバチと音を立てて燃える松の火が緊張感をうながす。80kgの松明を二人が担ぐ。その大松明がゆらゆらと動き始めた。
鞍馬太鼓の打ち鳴らす音と共に、大松明は集落内の街道を練り歩く。

午後8時、大松明が立ち上がる
そのあと鞍馬寺山門前に何百何十の大松明が続々と集まり、祭は最高潮に達する。
わたしたちはここでタイムリミット!まことに残念ながら、その光景を見ることができなかった。
大松明が立ち上がった光景をながめながら真っ暗な街道を下りはじめる。
明かりは徐々に小さくなってフェードアウトした・・・。

さあこれから、狭い街道を山門まで練り歩く
このあとの夜祭は想像の域を出ない。
大松明が燃え尽きたあと神輿を担ぎ出す。
参道の石段が急なため下る際は、スピードが出過ぎないように女性が綱を引く。この綱を引くと安産になると言われているようで、その綱が飾ってあるのを見た。
神輿の方は、2人の若者が担ぎ棒にぶら下がるチョッペンという儀式を行う。
よく知られていることば“割礼(かつれい)”のこと。これを経験して、男の子が大人になる。
神輿は集落内を練り歩いたあと御旅所へと戻される。それが0:00頃になり、さらに御旅所から由岐神社へ神輿の還御が2:00頃という。
やはり夜を徹しての祭だ。
いつか見極めてみたいという欲望が燃えたが、無理かなと思う自分がいた。
(2013年10月22日 鞍馬火祭り 「京都の秋(2)」へつづく)
Copyright ©2003-15 Skipio all rights reserved