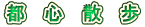
江戸東京たてもの園ー1
(東京都小金井市)
・・・江戸下町の情緒を味わう・・・
わが居住地小金井の北端・小金井公園にある「江戸東京たてもの園」を散策してみました。今ではなかなかお目にかかれないちょっと前の日本を覗き見することができました。貴重な近代史が残っていました。

たてもの園入場口は旧武蔵野郷土館
格式の高い立派な建物です
もともと小金井公園には「武蔵野郷土館」という博物館があり、いくつかの歴史的建造物がすでに移築復元されていました。それがいつの間にか名称が変わり、内容も充実、拡幅されていました。
調べてみると園の開業は1993年春。両国にある「東京都江戸東京博物館」の併設施設として構想されましたが、両国にそのスペースがなく、代替地として都立小金井公園が選ばれたということのようです。今上天皇が東京空襲を逃れて疎開されたという「武蔵野郷土館」は「たてもの園」に取り込まれる形となりました。

総武線両国駅のすぐ近くに聳える江戸東京博物館
海外からの賓客をご案内すると喜んでいただけます
東ゾーンの一角は明治・大正・昭和初期の建物が往時をしのぶように整然と立ち並び、よき時代の下町情緒にひたることができます。それではさっそく中にはいってみましょう!
<子宝湯>
最奥に豪壮な建物を構えていたのが銭湯「子宝湯」。

宮崎駿監督のアニメ映画「千と千尋の神隠し」で正体不明の魔女「湯婆婆」が経営する湯屋「油屋」のモデルとなった銭湯です。
懐かしい。昭和4年開業といいますが、足立区千住元町から移築されました。
当時は内風呂などという贅沢な設備は庶民の家庭にありませんでした。江戸時代ではありませんが、長屋のくまさん、はっつぁんが仕事帰りの汗を流しに立ち寄って、ご隠居さんを囲んで隣近所の噂話でくだをまいた。まさに浮世風呂。みんなが使うから実入りもよく、それゆえに設備投資も惜しげなく・・・神社仏閣に負けない唐破風(からはふ=中央部は弓形で、左右両端が反りかえった曲線状の破風)が玄関に乗っていました。
浴室にはタイル絵がはめ込まれていますが、山が、富士山ではなくヨーロッパアルプスっぽい図柄で、一瞬ハテナ?

<小寺醤油店>
佐渡味噌丸五特約店・小寺商店の看板が正面にかかっています。

右から書かれた看板の文字に風格があります
味噌も醤油も酒も
日本の伝統的発酵、醸造食品はなんでもありました
もちろんキッコーマンとヤマサの醤油も扱っています。

創業何百年ですか?
歴史を感じさせます
日本酒・月桂冠の一升瓶が円錐形の展示台の上に並んでいます。当時、酒は量り売りの時代でした。
日銭稼ぎの親父さんが仕事から帰ってきて、「おい、ぼうず、酒を3合買ってきてくれ!」と酒屋に走らせます。帰り道、一目散の坊やは石に蹴つまずいて大事な親父さんの酒を道端に撒いてしまいました。さあ、どうしよう!
こんな経験を持たれたお年よりは多いのではないでしょうか。
いたーい鉄拳をもらったかもしれません。
下の写真は当時の居酒屋で、下谷の言問通にあった「鍵屋」。江戸末期、安政3年の建物とか。

下谷の言問通といえば吉原が目と鼻の先です
こちらで一杯呑んで景気をつけた後・・・
さまざまな人間模様が展開されたに違いありません
<傘屋・川野商店>

川野商店は江戸川区南小岩にあった老舗の和傘問屋。
出桁(でげた)造という建築様式の木造2階建は、重厚な屋根や格子戸など、江戸の正統的な町屋を継承するもので大正15年に建てられました。戦前はずっと傘の卸問屋をやっていましたが戦後間もなく廃業し、住まいとして使われていたようです。
かつて小岩は和傘の町でした。通りには天日干しされる傘が並び、花を咲かせたようでした。勿論私は見たことはありませんが、ものの本によります。しかし、たくさんいた職人たちは洋傘に押されて廃業の運命にありました。時代の流れですね。今も昔も逆らえません。
川野商店も解体の運命が待っていましたが、都の学芸員に建物の保存を願い出たところ受け入れられて残りました。広い園内にはそういった幸運な建物ばかりが集められています。すでに取り壊されてしまいましたが、美智子妃の生家・正田邸もなんとかならなかったのでしょうか。
<武居三省堂・文具店>

先般川越でこんな造りの店を見かけました。
大正ロマンの趣があっていいなあ、
と思いましたが生活する方はいかがなものでしょうか

くれたけ墨と読み取れます
明治初期に創業した文具店です。当初は筆、墨、硯の書道用品の卸をしていましたが、後に小売店に転業し、絵の具や文具も扱うようになりました。けっして広くない店内の壁際には200本近くはいった桐の筆箱が整然と並べられています。
建物は関東大震災後に建てられた「看板建築」という様式で、前面が茶色のタイル貼りになっていて、腰折れ屋根という屋根の形にも特徴があります。千代田区神田須田町一丁目からお引越しです。昭和2年築。
<荒物屋・丸二商店>
荒物屋ということばを最近聞くことがありませんから、若い人にわかってもらえるでしょうか。しかしちょっと前までは、日常の食・住を中心とした生活必需品(台所用品)を店先に並べ、活況を呈したことは間違いありません。これらの商品がないと生活ができません。
丸二商店は神田神保町に店を構えたといいますから、古本屋めぐりの途中立ち寄った作家や著名人も多かったたことでしょう。
関東大震災後の建築で、武居三省堂と同じく「看板建築」様式によります。前面部の銅板の意匠は青海波(中国の青海地方の民族文様に由来する山岳文様)や一文字、網代(竹などを縦横に編んだ文様)などの文様を用い趣向を凝らしています。

このゾーンは庶民が暮らした下町情緒を醸し出しており、横丁のしもた屋からベーゴマや面子を手にした子どもたちが飛び出してきそうな雰囲気を感じます。いいですね。
当時は近所付き合いも親密で、みんな豊かではなかったかもしれませんが、家族が仲むつまじく暮らしていたでしょう。そんな時代を懐かしく思います。

防火水槽に縁台があります
夕涼みのヘボ将棋の勝敗は如何に?
下町ですネエ!
<続く>
(2)千人同心と豪農へ|(3)
Copyright ©2003-6 Skipio all rights reserved